はじめに
こんにちは。弁理士の平野泰弘です。商標登録の手続きについて、「どれくらい時間がかかるのか」「審査がうまく進むかどうか」など、不安に思われている方は多いのではないでしょうか。
実は、商標登録のプロセスは申請から審査、そして登録証が届くまで、いくつかのステップを踏んで進んでいきます。
今回は、令和7年度の最新情報を踏まえながら、商標登録にかかる期間や手続きの流れを、安心して準備できるように説明します。
本記事の主なトピック
- 出願から実際の登録までの大まかな期間
- 早期審査制度を利用するときの期間と注意点
- 登録後に知っておきたい「異議申立期間」
- 商標権の存続期間と更新手続き
この記事でわかること
- 出願から登録までにかかる期間の目安
- 特許庁の審査が実際にどのように進むのか
- 早期審査制度を使うべきかどうか
- 登録後に気をつけておきたい手続きと期間
それでは、順を追って解説していきます。最後まで読んでいただければ、今抱えている不安や疑問にきっとお役立ていただけると思います。
索 引
1. 出願してから登録されるまでの期間
商標登録をスムーズに進めるための準備が大切
商標登録は、特許庁(※商標登録などを審査する国の機関)に願書を出願してから、およそ8か月程度で登録されるのが一般的です。
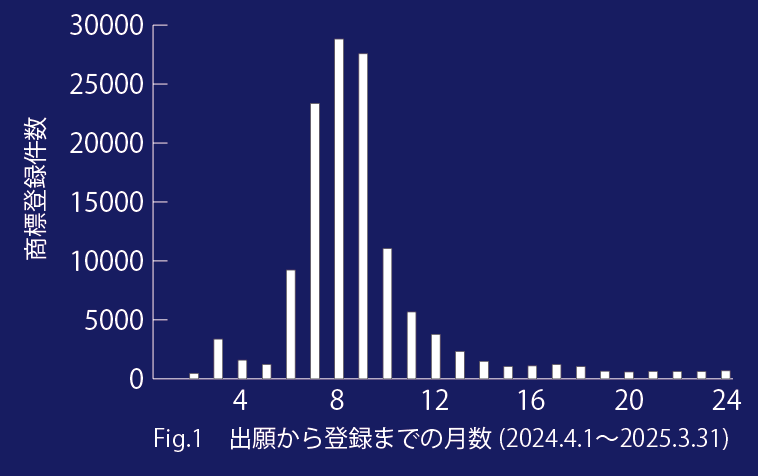
図1 出願日から、商標権が発生するまでの期間を示すグラフ
令和7年度の最新情報により、昨年(2024年)4月1日〜令和7年3月末の間に商標公報で発行された約14万件の商標について実際に私が調査したところ、多くのケースが8か月ほどで登録になっています。
ただし、最長では24か月以上かかった例もあるため、あくまで「目安」としてとらえてくださいね。
一方で、早期審査(後述します)を利用すれば3か月ほどで結果が出ることもあります。全体的には、約14か月程度で審査が終了する例が多いようです。
ポイント
- 出願準備をしっかり行うことで、審査落ちや書類の不備などを避けやすくなる
- 同じ商標を複数の人が出願している場合、先にきちんと手続きを済ませた人が優先される
出願前の下準備が重要な理由
「とにかく早く商標を取りたいから、急いで出願したい!」という気持ちはよくわかります。
ただし、書類作成のミスや似たような商標の見落としなどがあると、手続きのやり直しでかえって時間がかかり、ライバルに先を越される可能性もあります。
そこでおすすめしたいのが、弁理士(特許や商標など知的財産の専門家)の在籍する特許事務所へ事前に相談・調査を依頼しておくことです。
特に、どの区分(商品やサービスの分類)に出願すべきかは、経験がないと見落としがちですが、ここで失敗すると後々、保護したい範囲を逃してしまうこともあります。
身近な例
飲食店の名称を商標登録したいと思っていたのに、実際は飲料や食品販売にも展開予定。ところが、最初にその区分を登録し忘れてしまい、改めて追加出願すると二度手間になる…といったことが起こり得ます。
弁理士や特許事務所への調査依頼で安心をプラス
たとえば、ファーイースト国際特許事務所では、弁理士・弁護士が無料で商標検索調査を行い、弁理士登録10年程度以上の専門家があなたの直担当になります。
第三者がすでに権利を取得していないか、類似する商標がないかなどを事前に確認できるため、審査落ちを回避する可能性がグッと高まります。
こういった事務所なら、調査結果を報告書で提供してくれたり、疑問点を無料で説明してくれたりするので、専門知識がない方でも安心して進められるでしょう。
[無料商標登録調査]
2025年4月時点の審査待ち状況
特許庁では毎年膨大な数の商標出願が行われるため、「自分の出願はいつごろ審査されるの?」という不安がつきものです。令和7年4月時点の情報によると、出願された日や商品の区分によって、おおよその審査開始時期が公表されています。
| 分類 | 指定商品・役務の区分 | 出願日(令和6年) | 審査開始予定 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 化学 | 第1類〜第5類 | 8月~10月 | 4月 |
| 食品 | 第29類〜第33類 | 9月~11月 | 4月 |
| 機械 | 第6類〜第13類、第19類含む | 9月~11月 | 4月 |
| 雑貨繊維 | 第14類〜第28類、第19類除く | 8月~10月 | 4月 |
| 産業役務 | 第35類〜第40類 | 9月~11月 | 4月 |
| 一般役務 | 第41類〜第45類 | 8月~10月 | 4月 |
| 国際商標 | 国際登録に基づく指定通報案件 | 7月~9月(指定通報日) | 4月 |
こちらはあくまでも目安ですので、実際の審査開始は前後する可能性があります。
また、特許庁では願書を受理した後、まず形式面のチェック(住所や氏名の記載など)を行います。
書類に不備があると、修正(補正)するよう指示を受け、一定の期間内に対応しなければなりません。
この段階で対応を誤ると出願が却下されることがあるので注意してくださいね。
審査待ちの期間は「順番待ち」のイメージ
商標を扱う審査官は毎日何百件もの出願を確認しており、一年間で合計10万件以上の商標登録出願が特許庁に届きます。
実は、出願してから実際に審査官が内容をチェックし始めるまでの半年ほどは、「順番待ち」の状態なのです。
「なかなか結果が返ってこない…」と不安になる方もいるかもしれませんが、多くの場合は急ぎの要件がなければ問い合わせをしても特許庁から具体的な返答はないので、落ち着いて待つしかありません。
審査が始まってからは、一般的に出願から6〜11か月後に結果(登録査定または拒絶理由通知)が届きます。
商標の種類によって期間が変わる?
文字(単語)だけの商標と、ロゴや図形入りの商標とでは、大きく審査期間が変わるわけではありません。
ただし、音商標や色彩のみの商標といった比較的新しいタイプの商標については、やや慎重に審査が行われるため、1年以上かかるケースもあるようです。
個人と法人で審査スピードに差はあるの?
個人出願だからといって、法人(会社)出願よりも遅くなるといったことは基本的にありません。
差が出るとすれば、書類作成や調査の手間が出願を個人で行う際に負担が大きく、ミスが生じやすい点ですが、これはあくまで「書類不備による遅れ」であり、本質的に個人だから遅いというわけではないのでご安心くださいね。
他の人より結果が遅い…そんなときは?
商標登録出願後に審査の進捗が気になる場合、特許庁への問い合わせはできますが、未着手案件の詳細に関しては原則回答がありません。
また、FAXでの問い合わせは令和3年6月30日で終了しているため、最近では電話や電子出願システムを通じての確認という形になります。
ただし、問い合わせてもすぐ審査が進むわけではないので、「順番を待つものだ」と考えて焦らず過ごすのが一番です。
審査結果の通知
出願から半年程度で特許庁から審査結果が届きます。
合格の場合は「登録査定」という通知が来ますし、審査官から指摘や疑問があった場合は「拒絶理由通知」が届きます。
拒絶理由通知が来たときには、通常40日以内に意見書(反論)や補正書を提出して再審査をしてもらうことが可能です。
「ほんの少し直せば通りそう」という場合もあれば、「どう調整しても同じ名前の登録が先にあるので難しい」など状況はさまざま。対応方針は、弁理士等の専門家と相談しながら進めると安心ですね。
拒絶理由通知が届いたら
拒絶理由通知の内容をよく確認し、反論や補正の余地がありそうなら意見書を出します。
その後、1か月ほどで結果が返ってくることもあれば、審査官の都合などで半年ほど待つ場合もあります。
万が一、明らかに厳しい理由が示されていて「このまま意見書を出しても合格しない」と判断されたときには、新しい商標での出願を検討するのも一つの方法です。
無理に粘るより、早めに方針転換するほうが総合的にコストや時間の損失を抑えられるケースもあります。
登録査定の通知
合格(登録査定)の通知が届いたら、今度は「商標権を発生させるための登録手続き」と「登録費用の支払い」を、特許庁から指定された30日以内に行う必要があります。
ここは大学の入学手続きに例えられます。
合格通知(登録査定)が届いただけではゴールではなく、その後にきちんと入学金(登録費用)の支払いと入学手続き(登録手続き)を完了しなければなりません。
また、住所や権利者が変わっている場合はこの時点で手続きを行うと、不要な追加費用を抑えやすいです。
登録後に変更多数があると、まとめて処理できなかったり費用がかさんだりするので、合格通知を受け取った段階で必要な変更がないかを見直してみてください。
商標権の発生
登録手続きと登録料金の支払いが完了し、特許庁が設定登録を行えば、晴れてあなたの商標権が確立します。登録手続き後、およそ一週間前後で電子形式の「商標登録証」が発行されますので、大切に保管しましょう。
商標権を取得すると、無断で商標を使われた場合に警告や差止請求(使わないよう止める)、損害賠償を裁判で求めることが可能です。
また、自分が保有する商標を他社にライセンスして使用料を得たり、譲渡して収益を得たりといった活用もできます。
海外での商標権取得について
商標権はあくまでその権利を取得した国でのみ有効です。
海外に展開する場合、各国ごとに別途手続きが必要ですが、マドリッドプロトコル(マドプロ)という国際的な手続きによってまとめて申請する方法もあります。
ただし、マドプロで取得した権利は、日本の商標権が消滅すると海外での権利も連動して消滅してしまう場合があるため、まずは国内できちんと権利を固めることが大切です。
2. 早期審査制度を活用したときの期間
「なるべく早く登録を確定させたい」という方のために、特許庁では早期審査制度を設けています。
通常11か月ほどかかる登録までの期間が、早期審査の要件を満たせば2か月程度に短縮されるメリットがあります。
しかし、誰もがすぐに利用できるわけではなく、「すでに商品・サービスの販売や提供を準備している」「出願の区分が具体的に使用中である」といった一定の条件をクリアする必要があります。
早期審査のメリット・デメリット
- メリット: 短期間で審査結果がわかるため、競合他社に先んじて商標権による保護が受けられる
- デメリット: 使用していない商品・サービスは権利範囲から外すことを特許庁から求められる場合があるため、将来使うかもしれない区分を一度に押さえたい人には不向き
早期審査を受けるからといって、合格率が上がるわけではありません。
あくまでも「審査が早まる」だけですので、登録可否の判断は通常審査と変わりません。「先に出願したかどうか」で審査に合格できるかどうかが決まる点は同じです。
3. 商標登録の異議申立期間
無事に商標権が生まれても、登録後2か月間は第三者が「その商標登録に異議を申し立てる」ことができます。
これを異議申立制度といい、たとえば「実は自分が先に使っていた有名な商標と紛らわしい」「審査の段階で見落としがあったのでは?」という声が特許庁に寄せられれば、改めて登録の正当性を審理されるのです。
この審理には通常1年程度かかることが多く、場合によっては商標登録が取り消されてしまうこともあり得ます。
ただし、まったく心当たりがない場合や、正当性がある場合は問題ありませんので、ご安心ください。
4. 商標権の存続期間の満了について
商標権は一度取れば永久に続くわけではなく、登録日から10年ごとに更新手続きが必要です。
ただし、手続きをきちんと行いさえすれば、理論上は何度でも更新できるため、半永久的に保護を受けられます。
他の知的財産権(特許権は原則20年、意匠権は原則20年など)と比べても、商標権だけは更新を繰り返せる点が大きな特徴です。
更新忘れにご注意
もし更新時期を過ぎてしまうと、追加料金が発生したり、最悪の場合商標権が失効してしまいます。
特許庁からは特にお知らせが届かないので、自分で管理するか、依頼している特許事務所にサポートをお願いしておくのがおすすめです。
ファーイースト国際特許事務所では、出願から登録までサポートした案件について、更新時期が近づいたら連絡するサービスも行っています。
住所変更等があったときは知らせておけば、更新手続き漏れを回避しやすくなるでしょう。
5. まとめ — 安心して商標登録を進めるために
商標登録は、出願してから審査、そして登録が確定するまでにどうしても時間がかかります。通常であれば8〜11か月程度、混雑状況や個別事情によってはもっとかかることもあると考えておくとよいでしょう。
一方で、早期審査制度を活用すれば2か月ほどで結果がわかる可能性もありますが、要件を満たさないと利用できないことや、権利範囲が制限されるなどのデメリットもあるため、自身のビジネスプランに合わせて検討すると安心です。
また、取得後も異議申立期間(2か月)や10年ごとの更新手続きを忘れずに行う必要があります。いずれも難しい手続きではありませんが、そもそも出願時から弁理士や特許事務所にサポートを依頼しておくと、後々の見落としやトラブルをぐっと減らすことができます。
最後に
商標は、自分のビジネスやブランドを守る強い味方です。
「こんな初歩的な質問していいのかな?」と思わずに、一度専門家に相談してみてください。
分かりやすい解説や的確なアドバイスを受けられると、予想以上にスムーズに進むことも多いですよ。
ファーイースト国際特許事務所では、無料の商標検索調査をはじめ、皆さまが抱える不安や疑問に寄り添いながらサポートしております。安心してご依頼いただければと思います。
※この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に応じた法的アドバイスではありません。実際の手続きを行う際は、必ず専門家へ直接ご相談くださいね。
[無料商標登録調査]
不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
読んでいただき、ありがとうございました。あなたの大切なブランドが、しっかり保護されますように。
ファーイースト国際特許事務所


