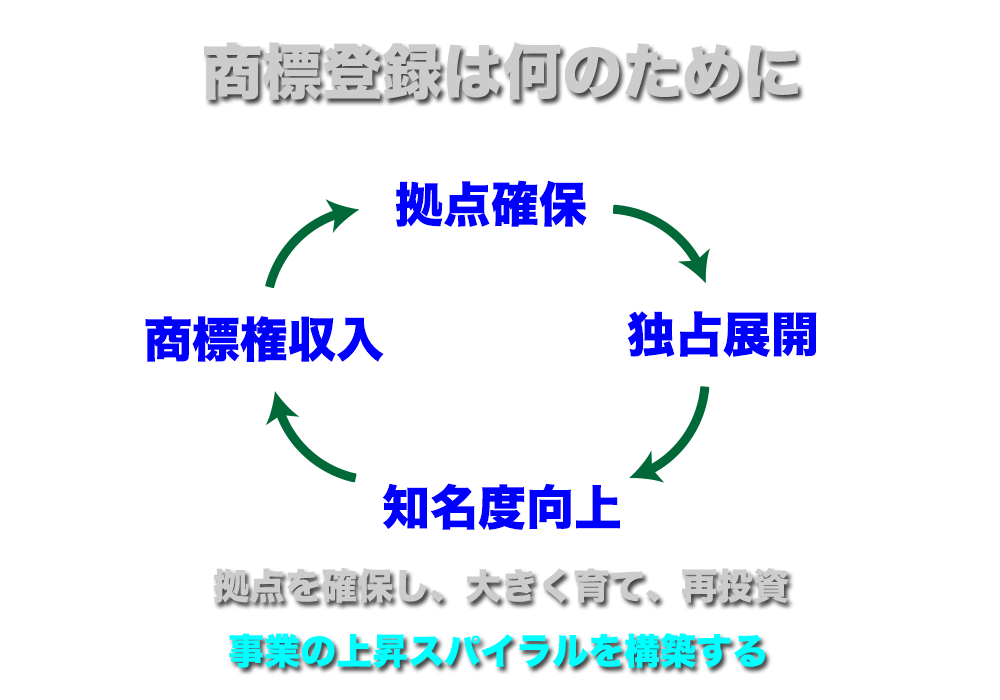1. はじめに
インターネット上には商標登録について詳しく解説しているウェブサイトが多く存在します。それらは弁理士による「商標法に基づいた商標登録の法的側面」を主に扱ったものや、特許事務所が展開する「実際の手続きを進める具体的な方法」を解説したものなど、様々な視点から情報が提供されています。
しかし、その多くが重視しているのは「どうやって商標登録をするか」であり、商標登録の真の目的、つまり「なぜ商標登録をするのか」を具体的に語るウェブサイトは驚くほど少ないのです。
あなたは「なるほど」と思うかもしれません。
「なぜ商標登録をするのか」がほとんど語られていないその理由は、弁理士・弁護士から見れば商標権を取得することは極めて自然な行為であり、無理に説明をしなくても理解してもらえると考えられているからです。
特に、商標登録の手続きをサポートする我々弁理士・弁護士にとって、その目的を説明する必要性を感じる状況は、クライアントから特に質問が出たときだけです。
これは例えば、コンビニエンスストアのウェブサイトが「なぜコンビニを利用すべきなのか」を説明したり、映画館のサイトが「なぜ映画を観るべきなのか」を明示したりしないのと同じです。
さらに、商標登録の目的について問題意識を持っていない人々が、わざわざ商標登録についてのウェブサイトを訪れることはまずありません。
逆に言えば、商標登録の目的を理解した上で情報を求める人々だけが、こうしたウェブサイトを訪れるわけです。
ウェブサイトを運営する側と訪れる側が、商標登録の目的について深く考え直す機会はそう多くはないのが実情です。
私自身、10年連続で商標登録出願の上位5位にランクインしていたことがあり、20年近く特許事務所を運営する所長として、商標登録の目的について理解しておいてほしいと思う重要なポイントがいくつかあります。
今回は、人にはなかなか聞けない「商標登録の目的」に関する4つの重要なポイントについて説明します。
2. 商標登録の目的その1:ビジネスの”お城”を構築する
他者が無許可であなたの商標権の範囲で商標を使用することを防ぐのが商標登録の最初の目的と言えます。
大きな視点から見れば、自社の名前、製品名、サービス名、企業ロゴ等を商標登録する意義は、ビジネスフィールドの確立のための重要な手段となる、と理解できます。
登録された商標権は、土地の権利の所有権と類似した性質を有しています。
例えば、他人が勝手に自分の土地に侵入したとき、許可なくこちらの土地に侵入することを阻止する権利があります。これは商標権においても同じです。
他人があなたの商標権に反する範囲で無許可で商標を使用する場合、個人、企業を問わず、その商標の使用を中止するよう要求することが可能です(差止請求)。
言い換えると、これは無許可であなたの保護区域に侵入することを禁止するということです。
さらに、無許可で自分の駐車場に車を駐車している他人に対して、その期間に対する駐車料を請求するのと同じように、商標権においても同じ権利があります。
あなたの商標権に反する範囲で無許可で商標を使用していた他人に対して、過去に発生した損害分を補償するよう要求することができます(損害賠償請求)。
これらの権利は商標法により規定されており、国により権利が保証されています。
商標権を有していない場合、他人に対して自分の使用している商標の使用を中止せよという商標法上の根拠がありません。
商標権を持たない者同士が、互いに反する範囲で各自の商標を使用していた場合、どちら側の視点から見ても、自分の商標が他人に無許可で使用されていると主張できますが、商標権がなければ優劣が付けられず、問題は簡単には解決しないでしょう。
しかし、商標登録をすませておけば、商標権を有している方が正義の立場に立つことができます。一方、正義の立場にない側は法に違反している悪者の立場となります。
ちなみに、商標権は、先に特許庁に商標登録を行った者に与えられます。誰かが先に商標の使用を始めたとしても、現行の法律の枠組みでは、先に商標を使用した事実だけでは商標権を持つことはできません。
商標を登録していなければ、あなたの商標を他人に無許可で使用された場合でも反論できない状況になります。これは、他人が自由にあなたの土地に出入りできる状態と同じです。
ビジネスが成功すれば、他人があなたの領地に無断で侵入し、そこで得られた成果を奪い取る可能性があります。
このような事態を避けるために、商標登録により他人が無許可であなたの領域に侵入しないようにし、まずはビジネスの”お城”を構築します。
3. 商標登録の意義その2:独占的な展開を可能にする
商標が登録された段階で、ビジネスの基盤が確保できます。他人があなたの商標を無断で使用することが禁止されるため、市場においてあなたの製品やサービスは同一商標を用いて独占的に展開できるのです。
(1)日本国内での独占的な商標使用
商標登録によって、登録された範囲内で日本国内であなたの商標を独占的に使用する権利が得られます。これを「専用権」と呼びます。
さらに、第三者があなたの商標権を侵害する可能性のある登録された範囲に類似する範囲で使用を防ぐ権利も得られます。これを「禁止権」と言います。
なお、日本の法律の範囲は日本国内に限られています。そのため、海外で商標権を守りたい場合は、基本的に各国で商標登録申請をする必要があります。
北海道のラーメン店と沖縄のラーメン店といった、商圏が全く重ならない場合でも、一方が他方の商標権を侵害する、その商標の使用は許されません。
さらに、商標権は10年ごとに更新が可能であり、この更新手続きを続けることで、理論的にはほぼ無期限に権利を保持することができます。
もし、あなたの商品が爆発的に売れた場合、その商品名が登録商標によって保護されていれば、他者はその商標を使用することはできません。本来、模倣商品を販売したいと考えても、オリジナルが次々と売れていくのを見るしかありません。
(2)商標登録をしなければ売上は時間とともに減少
商標登録をしないと、ビジネスは時間が経つにつれて苦境に立たされます。あなたのビジネスが成功すればするほど、無法者が侵入してきて商圏を乗っ取ろうとします。
これらの無法者があなたのビジネスを引き寄せ、時間が経つにつれてビジネスが侵食される結果となります。商標登録により、しっかりと基盤を築き、全国規模でビジネスを独占展開することが求められます。
かつては全国規模でのビジネス展開は大企業独壇場でしたが、現在ではインターネットにより地域の壁を越えて小規模事業者でも商圏を広げることが可能となりました。
(3)独占展開における注意点
商標を登録し、ビジネスを独占的に展開する前に注意すべきポイントがあります。
それは商標について学習が進んでいない場合には、「強い商標」ではなく、「弱い商標」を選択しようとする傾向があることです。「弱い商標」とは、製品や業務そのものの一般名を指すものです。例えば、タクシー事業に「観光タクシー」の商標を、果物販売に「みかん」の商標を使用するなどです。
大規模なビジネスは「強い商標」を、小規模なビジネスは「弱い商標」を選ぶ方が有利だと思われがちです。
しかし「弱い商標」はじわじわとあなたのビジネスを侵食します。商標権を得られないため、時間が経つにつれて無法者の参入が増え、売上が減少します。
そのため、最初からしっかりと「強い商標」を選択することが重要です。
4. 商標登録のメリットその3:ブランドの認知度を上げる
商標を登録し、その商標を使ってビジネスを展開すると、時間が経つにつれてその商標の認知度が上がります。
具体例として、コンビニでアイスクリームを購入する状況を考えてみましょう。
最初はどのアイスクリームがおいしいのかわからないので、見た目やイメージでアイスクリームを選びます。
しかし、時間が経つにつれてお気に入りのアイスクリームが見つかるでしょう。私のお気に入りは「明治エッセルスーパーカップ」です。
現在では、アイスクリームを選ぶ際、私は「明治エッセルスーパーカップ」を選びます。家族がアイスクリームを買ってくるときも、「明治エッセルスーパーカップ」を指名します。
このように「指名される」ことは、ビジネス展開において非常に重要なポイントです。
お店が本当に売りたい商品は、利益率の高い商品です。簡単に言うと、低コストで仕入れて高価格で販売できる商品です。
しかし、私たち消費者はお店の利益率には興味がありません。私たちが「明治エッセルスーパーカップ」が欲しいと言えば、どのお店も「明治エッセルスーパーカップ」を提供せざるを得ません。
こういった指名買いを生み出すものこそが「強い商標」の一例です。
一方、「弱い商標」は、「カップアイス」など商品カテゴリーそのものの名称です。商標について詳しくない初期段階で、多くの人が弱い商標を自社の商標として選びます。
弱い商標は商品自体を説明する役割を果たしているため、その商品が何であるかを顧客に説明する必要がないからです。
仮にあなたがアイスクリームを商品として扱っていて、「カップアイス」という商標をつけたとしましょう。
このような商標を特許庁に登録申請しても、基本的には審査には通りません。「カップアイス」は一般的な表記であり、一部の人に独占させる理由が存在しないからです。
なお注意が必要なのは、「カップアイス」が商標の一部として含まれている場合、その商標が登録される可能性があるということです。これは、地名「東京」が商標の一部として含まれていても、その全体が地名表記でなければ登録される可能性があるのと同じです。
仮に商標登録ができないまま商品を発売した場合、市場に他社から同じような「カップアイス」の商標をつけたアイスクリームが出てきても、それを阻止する手段がありません。
商品が売れれば売れるほど、「カップアイス」の商標をつけた事業者が増え、売上は事業者数に分散されるため、時間と共に売上は下がっていきます。
これに対して、強い商標は消費者から「指名買い」を受けるため、他社の市場参入があっても、すでに認知度を上げて指名買いが可能な状態を作り上げていれば、弱い商標の場合に比べて影響を受けにくいのです。
5. 商標登録の目的その4:商標権からの収益を獲得する
商標権自体にも価値があることはあまり知られていませんが、実際には大きな収益源となり得ます。
最初に述べたように、商標権は土地の所有権と似た性質を持ちます。登録商標が一定の認知度を得ると、商標権のライセンスを求めるとか、その商標権を買いとりたいという人々が出てきます。
土地の所有権と同じように、商標権をライセンスし(つまり貸し出し)、収益を得ることも、売却し(有償で権利を移転する)、収益を得ることも可能です。
私のクライアントの中には、商標権のライセンス収入だけで、実質的に生活費全体を賄っている方もいます。
つまり、ある一定の認知度を持つ登録商標は、それ自身が価値を生み出す存在となります。商標登録は、本質的には、商標権自体に価値を生み出させるために行う作業であると言っても過言ではないでしょう。
次に、商標権からの収益を増やす方法について、宅配業を例にして考えてみましょう。
(1)フロービジネスの事例:宅配業
宅配業では、配達できる荷物の量が売上を決める要素となります。しかも、宅配業者は、荷物を届けることによってのみ収入を得ています。
このように、働いた分だけ収入が得られるビジネスを「フロービジネス」と呼びます。
フロービジネスの問題点は、実質的に自分の時間をお金に換えていることです。ビジネスに真剣に取り組むほど収入は得られますが、自身がそのビジネスに縛られてしまうという問題があります。
(2)フロービジネスからの転換事例:宅配業からフランチャイズビジネスへ
一人で宅配業を経営していた人が、そのノウハウをまとめてパッケージ化し、商標権を活用して同じビジネス形態でライセンス業を行うとしましょう。
ライセンシー(ライセンスを受ける者)が一定数集まると、ライセンサー(商標権者であり、ライセンスを行う人)は、自身が宅配業を行わなくても生活できる収益基盤を得ることができます。
そうすると、自分自身が自分の現状のビジネスに縛られることがなくなります。時間に余裕ができるため、次の拠点確保、独占展開、知名度向上、商標権収入に向けたサイクルを回し始めることができます。
このようにして、現状のビジネスを拡大させていきます。
働いた分だけの収入が得られる「フロービジネス」から脱却し、あなた自身が直接時間を提供しなくても収益を得られる「ストックビジネス」を展開します。
「ストックビジネス」は、一定期間働いて構築した収益構造が、ある時点以降、その構造自体が収益を生み出すビジネスの枠組みを指します。
ここでは商標権を中心としたライセンス収入によるストックビジネスに焦点を当てましたが、他にもストックビジネスの形態は無数に存在します。要はアイデア次第ということです。
(3)事業の上昇スパイラルの後は、商標権を軸とする事業一括売却による脱却も可能
商標権を活用しないビジネスの場合、あなた自身が自身のビジネスに束縛され、現状から進展することが難しいでしょう。
しかし、商標権を利用したストックビジネスでは、商標権を有償で移転できる性質を活用し、それぞれの商標権で構築したビジネスを一括売却することで、現状のビジネスから脱却し、次のステージに進むことも可能になります。
本業で稼ぐだけでなく、本業を支える商標権の価値を増大させて、その商標権自体が価値を生み出すように事業の運用設計を考える必要があります。
6. 商標登録の目的についてのよくある質問
Q1. 商標登録は何のために必要ですか?
A:商標登録は、ビジネスのブランドを保護し、他社による無断使用を防ぐために重要です。自社の商品やサービスが特定の商標と認識されることで、消費者との信頼関係を確立し、ビジネス価値を高めることが可能になります。
Q2. 商標登録しないとどんなリスクがありますか?
A:商標を登録しないと、自社のブランド名やロゴが他社に無断で使用される可能性があります。その結果、混乱を招くことやブランド価値が低下することがあります。さらに、他社が同様の商標を先に登録した場合、自社の商標の使用を制限されるリスクもあります。
Q3. 商標登録はどれくらいの費用がかかりますか?
A:商標登録の費用は、登録したい国や地域、商品やサービスのクラス数、弁理士の手数料などにより異なります。そのため、具体的な費用は特許事務所に相談することをおすすめします。
Q4. 商標登録が承認されるとどうなりますか?
A:商標登録が承認されると、その商標の使用権が法的に保証されます。他社があなたの商標を使用しようとした場合、法的措置を取ることが可能になります。また、商標権はライセンス販売や売却など、収益化の手段としても利用可能です。
Q5. 商標登録の適用範囲はどれくらいですか?
A:商標登録の適用範囲は、登録した国や地域に限られます。したがって、複数の国や地域で商標を保護したい場合は、それぞれで登録する必要があります。国際的な商標保護のためには、マドリッド議定書などの国際的な制度を利用することも可能です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247