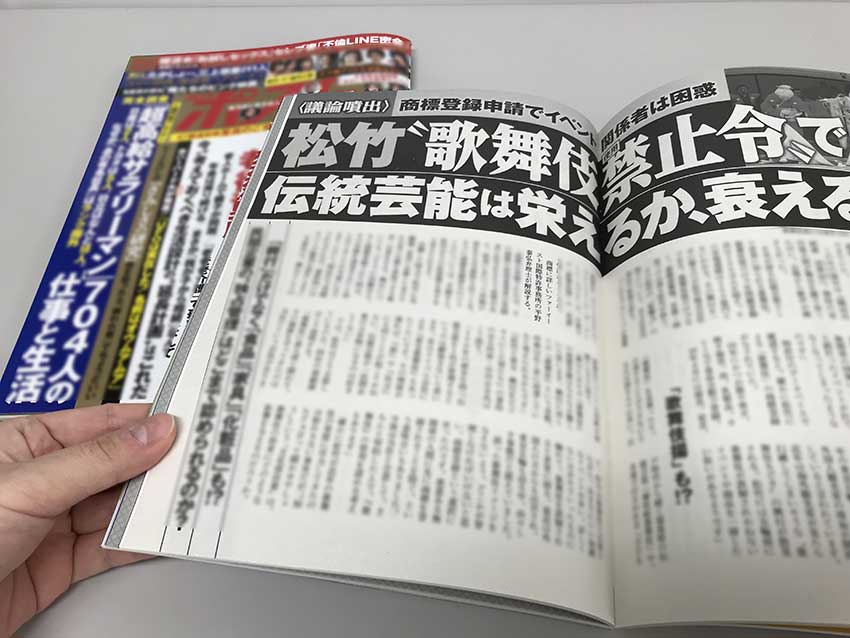1. そもそも商標「歌舞伎」は登録できるのか
販売する商品や業務を指定して商標登録する制度
株式会社松竹が、以前「歌舞伎」という商標について権利を取得しようとしていることに、多くの方が疑問を感じたのではないでしょうか。伝統芸能の名称を一企業が独占するというのは、確かに違和感があります。
特許庁で登録される商標権は、その言葉自体を無制限に独占する権利ではありません。
商標権は、権利設定の際に指定した商品やサービスに関連する範囲に限って効力を持ちます。
つまり、同じ「歌舞伎」という言葉でも、指定する商品やサービスが異なれば、それぞれ別の商標として登録できるのです。
たとえば、「歌舞伎」という言葉が一般的な表現だとしても、お菓子の販売分野では必ずしも一般的とは言えません。
歌舞伎という言葉とお菓子との間には直接的な結びつきがないため、お菓子を指定商品として「歌舞伎」の商標登録を申請すれば、審査に合格する可能性があります。
お菓子との関係に限れば、歌舞伎という商標が一般的な表現とまでは言えないからです。
このように商品やサービスを限定して商標登録する制度があるため、「歌舞伎」について商標登録すること自体が不当だとは一概には言えません。
実際、特許庁では多数の「歌舞伎」商標が審査を通過して登録されている実績があります。
2. 歌舞伎が商標登録されるとどうなるのか?
商標権の制限を受けるのは業務上の使用に限られる
特許庁に商標登録を申請し、無事審査を通過すると商標権を取得します。登録された商標は権利者だけが使用できるため、商標権者の許可なく第三者が勝手に「歌舞伎」の商標を使用することは制限されます。
ただし、商標権を取得したからといって、その言葉の使用を全面的に禁止できるわけではありません。
商標権が存在しても、自由にその商標を使える場合が数多くあります。
商売と関係ない場合の商標使用は自由
商標法は事業者同士の秩序を守るための法律です。そのため商標権が発生しても、事業と関係のない場面で商標を使っても商標権の侵害にはなりません。
ここで注意したいのは、個人使用だから常に許されるというわけではない点です。
個人事業主が事業として商標を使えば商標権を侵害するケースも出てきます。
商標権侵害の判断基準は、個人か法人かではなく、事業と関連して使っているかどうかです。
文字表記以外の形での使用は制限されない
「歌舞伎」の文字やマークを商標登録出願の願書に記載して商標権を取得した場合、その文字やマークを業務上の目印として使用することが制限されます。
これに対し、言葉として歌舞伎に言及するだけの場合は、商標権の侵害を理由に訴えられることはありません。商標権が保護するのは、商品やサービスの出所を示す標識としての使用だからです。
論評や意見表明での使用も自由
歌舞伎についての論説や意見を業務として発表する場合も、商標権の侵害にはなりません。商標法で保護される商標は、営業表示、つまり誰が商品やサービスの提供者かを示す印として使われるものに限られます。
単に伝統芸能について言及したり評論したりするだけでは、法律上の登録商標の使用には該当しません。論評や意見を述べることは自由です。
自己の氏名を通常の方法で使う場合も問題ない
仮に個人の苗字が「歌舞伎」である方や、読み方が「カブキ」である方がいたとしても、自身の氏名を通常の方法で使用する限り商標権を侵害しません。
氏名は先祖代々受け継いできたものです。それにもかかわらず、後から発生した商標権により自分の氏名が使えなくなるというのは本末転倒です。そのため、商標法には自己の氏名を使用する場合の例外規定が設けられています。
3. 伝統芸能の「歌舞伎」は商標登録できるのか
株式会社松竹は伝統芸能分野の業務にも「歌舞伎」を出願しみてたが
株式会社松竹は、伝統芸能の業務分野についても「歌舞伎」の商標を特許庁に出願しました。
商標「歌舞伎」の株式会社松竹による出願内容は以下のとおりです。
出願番号:商願2016-061086
結論から申し上げると、この出願は特許庁の審査で合格できず、最終的に拒絶査定が確定しています。
伝統芸能の業務分野では「歌舞伎」の商標の独占を、一企業には認めないという判断が下されたのです。
商標権という概念は分かりにくいのですが、土地の権利に例えると理解しやすくなります。
土地にも、勝手に入ることのできない私有地と、誰もが自由に入ることのできる公園などの公有地があります。
商標にも同様に、商標権が発生していて他人が勝手に使えないものと、誰もが自由に使えるものがあります。
誰もが自由に使える商標としては、地名表記としての「日本」「東京」「大阪」「名古屋」や、品質表示としての「安い」「おいしい」「高品質」などが該当します。
「歌舞伎」という商標も古くからある伝統芸能の名称です。一営利企業が伝統芸能についての表現を独占してしまうのは、公共の利益に反する可能性があります。
しかも商標権は更新手続により、未来に向かって半永久的に存続する権利です。
一度株式会社松竹が商標登録してしまうと、他の団体は同じ分野で「歌舞伎」の商標権を取得できず、株式会社松竹だけが「歌舞伎」の表現を自由に支配できることになってしまいます。
実際、商標法にも、業務との関係で一般的な語句にすぎない商標は登録を認めない旨の規定が存在します(商標法第3条)。
広く国民に商標「歌舞伎」が株式会社松竹のものと認識されている実績があるか
一方で、法律の規定を杓子定規に当てはめた場合も問題が生じます。
伝統芸能である歌舞伎の商標を誰のものでもなく、誰もが自由に使える商標であると法律上認定したなら、悪徳業者や質の低い業者でも「歌舞伎」の商標を掲げて伝統芸能のまねごとをすることが可能になってしまいます。
実際には、地道に伝統芸能である歌舞伎の歴史を、莫大な経済的負担を負いながらここまで育ててきたのが株式会社松竹です。その実績は法律上保護に値するという考え方も成り立ちます。
広く国民から「歌舞伎といえば、株式会社松竹だよね。」と認識される状態に達している場合には、例外的に株式会社松竹が伝統芸能の業務分野について「歌舞伎」の商標の権利を取得できる可能性も理論上は存在します。
権利取得前でも権利行使を予告すること自体は違法ではない
特許庁に商標登録を出願した後に、商標権を侵害する範囲で商標を使っている他の業者に対して株式会社松竹が「商標登録が認められたなら、それなりの対価をいただきます」と警告すること自体は違法行為ではありません。
ただし、最終的に特許庁で登録が認められない結論になったのであれば、株式会社松竹はその商標についての権利をすべて失います。
4. まとめ
この案件は特許庁でも相当悩ましい判断だったことは間違いありません。審査期間は異例の2年以上にも及びました。最終的な判断は、登録を認めない拒絶査定という結論で決着しています。
ここで注意したいのは、今回の結論は「歌舞伎」の文字そのものを独占できるかどうかを争った案件だという点です。
「歌舞伎」以外に、図形などの要素が加わると、図形も含めた全体で一つの商標権になります。そのため、「歌舞伎」の文字だけを独占することにはならず、審査に合格できる場合が出てきます。
また、指定する権利範囲としての指定商品役務が、伝統芸能以外を指定している場合は、伝統芸能を独占することにはなりません。こちらも同様に審査に合格できる場合が出てきます。
私のコメントは、2018年の週刊ポストで松竹「歌舞伎使用禁止令」として掲載されました(12月14日号)。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247