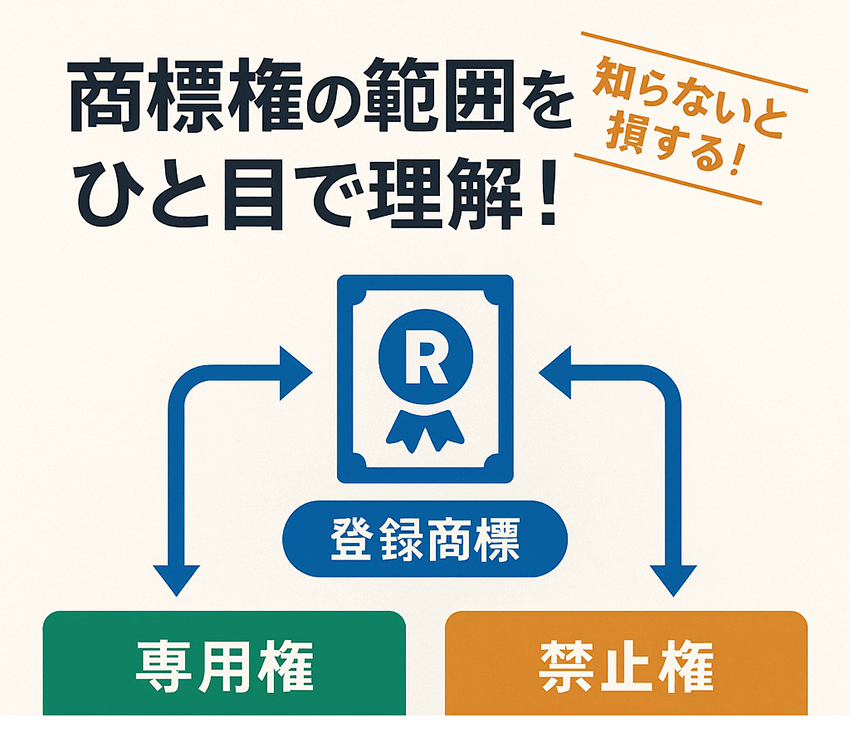索 引
1. はじめに — なぜ「範囲」の理解が重要なのか
「商標登録が終われば自社ブランドは完全に守られる」そう思っていませんか?
実は、事業者の中には「商標権を取得した」という安心感から、実際には守られていない領域に気づかないまま、ビジネスを展開しているところがあります。手続きは終わったけれども「登録したのに守られていなかった」というケースです。
願書に記載しなかった商品役務の権利は守られませんし、重要な商品役務の範囲は時代や流行等とともに変化していきます。
あなたの会社のブランドは、本当に守られていますか?
本記事では、商標の「専用権」と「禁止権」という2つの権利範囲を理解することで、あなたのビジネスの知的財産を適切に保護する方法をご紹介します。これを読めば、「どこまでが自社の権利なのか」が明確になり、無駄な訴訟リスクや模倣被害から自分を守る、転ばぬ先の杖になります。
2. 専用権と禁止権 — 基本用語を整理しよう
商標権には「専用権」と「禁止権」という二つの顔があります。この違いを理解することが、自社ブランドを守る第一歩です。
専用権とは
登録された商標を指定された商品・役務(サービス)について、独占排他的に使用できる権利です。
禁止権とは
自分の登録商標と同一または類似の商標を、指定商品・役務と同一または類似の範囲で他者が使用することを禁止できる権利です。
簡単に言えば、専用権は「自分だけが使える権利」、禁止権は「他人に使わせない権利」です。この違いは、自社ブランドの保護範囲を決定する重要な要素なのです。
3. 専用権の射程:商標も商品役務も” ドンピシャ同一 “の世界
適用範囲
専用権が及ぶ範囲は実際は狭く、「商標が同一」かつ「指定商品・指定役務が同一」の場合に適用されます。
例えば、「SAKURA」という商標を商品「洋服」について登録した場合、「SAKURA」という全く同じ文字を「洋服」という全く同じカテゴリーで使うことだけを独占できます。「SAKURA」をわずかに変えた「ZAKURA」や、「バッグ」などの類似商品への使用は、専用権の範囲外となってしまいます。
実務上のメリット
専用権の最大の強みは、その絶対的な効力です。水戸黄門の印籠のように、出せば勝てます。
登録商標と全く同じものを指定商品・役務と全く同じ範囲で使用している侵害者に対しては、裁判でほぼ100%勝利できます。税関での模倣品の差し止めなども、専用権に基づく場合はスムーズです。
登録時にすべき工夫
専用権を最大限に活かすには、出願時の工夫が必要です。
- 1. 指定商品・役務を過不足なく記載する:ビジネスの将来展開も見据えて、必要十分な範囲を指定
- 2. 商標の表記のバリエーションを押さえる:主力商標については、他社と類似するしないの争いがないように複数のバージョンを登録
- 3. 追加出願も検討:予算と保護範囲のバランスを考慮し、核となる商品・役務を優先的に保護し、後追いで補強
4. 禁止権の三つのパターン:広がるグレーゾーン
禁止権は専用権よりも広い範囲で機能しますが、その範囲は「類似」という曖昧な概念に依存します。
パターン1:商標同一 × 指定商品・指定役務類似
例:商標「SAKURA」で商品(洋服)の商標権者が、他社の商標「SAKURA」(コート)の使用を差し止める
商品の「洋服」と「コート」は、互いに同一ではありませんが、商品のカテゴリーとして類似するので権利範囲に入ります。
パターン2:商標類似 × 指定商品・指定役務同一
例:商標「SAKURA」商品(洋服)の商標権者が、他社の「さくら」(洋服)の使用を差し止める
商標の「SAKURA」と「さくら」は、アルファベットか平仮名かの違いがあるので同一ではありませんが、商標権の効力は同じ読み方の商標に及びます。文字の種類が違っても商標全体の読み方は同じなので、権利範囲に入ります。
パターン3:商標類似 × 指定商品・指定役務類似
例:「SAKURA」(洋服)の商標権者が、他社の「さくら」(コート)の使用を差し止める
商標の「SAKURA」と「さくら」は同一の表記ではないですし、商品の「洋服」と「コート」も同一の表記ではないです。
上記の場合と同じで、これらの商標同士の関係も、商品同士の関係も類似範囲に入るので、権利範囲に入ります。
これらのパターンは、「類似」という主観的な判断に基づくため、グレーゾーンが生じやすく、争いになりやすい領域です。
5. 専用権・禁止権の外側 — セーフゾーンは本当に安全?
「商標非類似 × 指定商品・指定役務非類似」の領域は、原則として商標法による規制を受けません。たとえば、「SAKURA」(洋服)に対して、「MOMIJI」(レストラン)は全く別の商標・商品役務であるため、自由に使用できるでしょう。
しかし、このセーフゾーンがときに安全とは限りません。以下のような法律による規制を受ける可能性があります:
- 1. 不正競争防止法:著名商標の希釈化や混同惹起行為として規制される可能性
- 2. 景品表示法:誤認混同を生じさせる表示として規制される可能性
- 3. 著作権法:ロゴが著作物として保護される場合
- 4. 一般不法行為:社会的信用を毀損するような使用
特に著名なブランドの場合、商標法の範囲外でも様々な法的手段で保護される可能性が高まります。
6. 類似判断の実務ポイント
類似群コードの読み解き方
特許庁の「類似商品・役務審査基準」では、商品・役務を類似群コードというグループに分類しています。同じ類似群コードに属する商品・役務は原則として類似と判断されます。
例:
- 17A01:洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類
- 21C01:かばん類、袋物
しかし、これはあくまで原則であり、実際の取引の実情によっては異なる判断がなされることもあります。
取引の実情・需要者の認識がカギを握る理由
類似性の判断では、以下のような「取引の実情」が考慮されます:
- 商品の販売場所が同じか(百貨店の同じフロアなど)
- 需要者(顧客層)が重なるか
- 業界の慣行として関連性が強いか
” パクられた! “と感じたらまず確認すべきチェックリスト
- 1. 相手の商標表記と自社商標を比較(外観・称呼・観念で類似性を検討)
- 2. 相手の商品・サービスと自社の指定商品・役務を比較
- 3. 類似群コードを確認
- 4. 取引の実情(販売チャネル、顧客層など)を分析
- 5. 混同の事実や可能性を示す証拠を収集
- 6. 相手方の使用開始時期と自社の商標登録日を確認
7. 裁判例で学ぶ” 境界線 “
スナックシャネル事件のドラマ
お酒を提供するスナックが店名にシャネルを使った事例で、実際に本家本元のシャネルから裁判で訴えられた事例があります。
本家本元のシャネルは、香水等で有名ですが、香水等とは関係がない飲食業の業務の使用中止を求められるのかが争われました。
商標権の場合は、本家本元のシャネル側が飲食業で商標権を押さえていないと飲食業の業務についてまでは商標権の効力は及びません。
スナックシャネル事件では、不正競争防止法で、スナックの店名にシャネルの商標を転用するのは認められないとの判決がありました(最高裁平成10年9月10日第一小法廷判決)。
このため、商標権の権利の範囲外だからといっても安全というわけではなく、他社の有名な商標に関連する権利と抵触しないかの検討も必要になります。
8. 企業が取るべき五つの実務アクション
1. 出願時に広めの指定範囲を設定
将来の事業展開を見据えて、現在の事業領域だけでなく、今後進出する可能性のある分野も含めて指定商品・役務を選定しましょう。予算との兼ね合いもありますが、コア事業に近い領域は広めに押さえておくことが重要です。
後で事業拡張をする際に、拡張した部分にすっぽり権利の抜けがあるとトラブルの元になります。
2. 定期的な類似商標ウォッチング
少なくとも四半期に一度は、他社の類似商標が出願・登録されていないかチェックする習慣をつけましょう。早期発見が訴訟コストの削減につながります。特許庁の「J-PlatPat」や民間の商標ウォッチングサービスが利用できます。
3. ライセンス契約で権利行使を補完
攻めの戦略として、類似領域でのライセンス契約を積極的に進めることも有効です。ライセンシーが市場を埋めることで、第三者の参入余地を狭めることができます。
4. 不正競争防止法とのダブルガード
商標権の範囲外でも、著名商標であれば不正競争防止法による保護が期待できます。そのためには、自社商標の周知性・著名性を高める広告宣伝活動と、その証拠の蓄積が重要です。
5. 侵害予兆を察知したら即・専門家へ相談
「様子を見よう」は禁物です。侵害の兆候を察知したら、早期に弁理士や弁護士に相談しましょう。警告書の発送タイミングや内容は専門家の助言を仰ぐことで、後の訴訟を有利に進められます。
9. よくある誤解 Q&A
Q: 「®を付けていれば大丈夫?」
A: ®マークは単なる表示に過ぎず、これを付けるだけでは保護範囲は広がりません。実際の権利範囲は登録内容によって決まります。
Q: 「類似群コードが違えば安全?」
A: 類似群コードは審査の目安であり、絶対的な基準ではありません。実際の取引実情によっては、異なる類似群コード間でも類似と判断されて、商標権侵害の問題が生じることがあります。
Q: 「表記を変えれば逃げ切れる?」
A: 「SAKURA」と「さくら」のように表記を変えても、称呼(読み方)や観念(意味合い)が類似していれば、商標の類似性は認められます。外観・称呼・観念の総合的な判断が行われるのです。
10. まとめ — ” 境界線 “を知ってブランドを守ろう
専用権と禁止権の違いを再確認
- 専用権:「同一商標×同一商品役務」という、どんずばりの範囲で絶対的な効力
- 禁止権:「類似」という概念を含む広い範囲で他社を排除する効力を発揮するが、判断にグレーゾーンあり
今すぐ実行すべき三行まとめ
- 1. 自社商標の登録範囲を確認し、不足があれば追加出願を検討する
- 2. 定期的な類似商標ウォッチングを習慣化する
- 3. 侵害の兆候があれば即座に専門家に相談する
実はあなたの商標、守り切れていないかも? 専用権と禁止権の境界線、知らないと損します!
コメント・シェアのお願い
この記事が役に立ったという方は、ぜひコメント欄でご感想やご質問をお寄せください。また、同じ悩みを持つ経営者・担当者の方にシェアしていただければ幸いです。