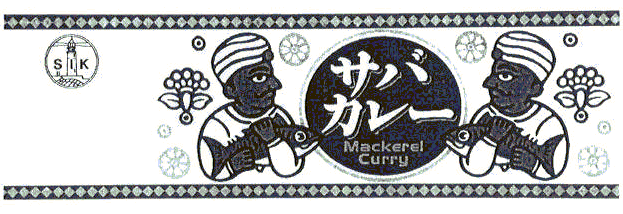身近な食材であるサバの缶詰が、ここ数年で価格が大きく変動しています。かつて150円程度で購入できたサバ缶は、ロシアのウクライナ侵攻以降、一時は300円近くまで値上がりしました。現在は近所のスーパーでは250円程度に落ち着いていますが、それでも以前と比べると高価になっています。
健康的でタンパク質を豊富に含むサバ缶は、多くの人に愛されている食材です。この価格高騰の背景には何があるのか、そして「さば」に関連する興味深い商標について、商標登録の観点から見ていきましょう。
1. サバの不漁がもたらす缶詰生産への影響
2024年8月7日の日本経済新聞によると、魚の缶詰生産量は71年ぶりの低水準となり、価格は5年間で2倍に上昇したと報じられています。この報道は、私たちの食卓に身近なサバ缶が直面している深刻な状況を示しています。
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会の統計データを見ると、サバの缶詰・びん詰の生産量は大幅に減少しています。2019年には44,878トンだった生産量が、2024年には21,328トンまで落ち込み、わずか5年間で半分以下になってしまいました。
一方、まぐろ・かつお類の生産量は、2019年の31,345トンから2024年の29,280トンへと微減にとどまっています。5年前はサバが生産量で優位でしたが、現在ではその立場が逆転している状況です。
マサバ太平洋系群の漁獲量の推移を見ると、さらに長期的な減少傾向が明らかになります。1970年代には100万トンを超えていた漁獲量が、2023年には7万トン台まで減少しているのです。
サバは、血液をサラサラにする効果や動脈硬化予防が期待されるオメガ3脂肪酸、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)を豊富に含むことから、健康志向の高まりとともに一時はブームとなりました。しかし、現在では需要に応えることが困難な状況に陥っています。
2. サバ愛好家のための特色ある商標
生産量の減少という厳しい状況にありながらも、サバを愛する人々は依然として多く存在します。ここでは、そんなサバ愛好家の期待を裏で支える、特色ある商標をご紹介します。
鯖専用日本酒「サバデシュ」
特許庁の商標公報より引用
茨城県水戸市の吉久保酒造が開発した「サバデシュ」は、その名の通り「鯖専用」として開発された日本酒です。サバの味わいをより引き立てるように仕上げられたこの商品は、意外な組み合わせが話題を呼んでいます。
茨城県とサバの関係については、あまり知られていないかもしれません。実は茨城県は、都道府県別のサバ漁獲量で1位か2位を争う、隠れたサバ大国なのです。地元の特産品を活かした商品開発の好例といえるでしょう。
とろさば料理専門店「SABAR」
特許庁の商標公報より引用
メディアでも頻繁に取り上げられる「SABAR」は、サバ料理の概念を変えた専門店です。このお店で提供されるのは、通常のサバよりも大きく、脂がたっぷりとのった「とろさば」です。
従来のサバ料理といえば、しめさば、焼きさば、さばの味噌煮といった和食の定番メニューが中心でした。しかしSABARでは、これらの定番料理に加えて、グラタン、ユッケ、サバサンドといった創作メニューも楽しめます。
各店舗では、その土地ならではのオリジナルメニューも提供されており、サバ料理の新たな可能性を追求し続けています。
サバカレー
特許庁の商標公報より引用
遠い昔のあるテレビドラマに登場したことがきっかけで商品化され、爆発的なヒットとなった「サバカレー」。多くの方にとって懐かしい商品かもしれません。ブームから時間が経った今でも、安定した人気を保ち続けている息の長い商品です。
サバとカレーという一見意外な組み合わせが、実は相性抜群であることを証明した商品として、食品業界に大きなインパクトを与えました。
3. 日本の魚食文化の変化とサバの将来
水産庁の統計によると、食用魚介類の1人1年当たりの消費量は23.4kgとなっています。この数字は年々減少傾向にあり、深刻な魚離れが進んでいることを示しています。
「食料需給表」のデータを詳しく見ると、食用魚介類の1人1年当たりの消費量(純食料ベース)は、平成13(2001)年度の40.2kgをピークに減少を続けています。そして平成23(2011)年度には、歴史上初めて魚介類の消費量が肉類の消費量を下回るという転換点を迎えました。
長い歴史を持つ日本の魚食文化は、今、大きな変革期を迎えています。サバの煮付けをはじめとする伝統的な魚料理が、若い世代の食卓から姿を消しつつある現状は、魚を愛する者にとって寂しいものです。
一方で、「サバデシュ」や「SABAR」、「サバカレー」のような商品や店舗の登場は、サバの新たな魅力を発信し、魚食文化の継承に貢献しています。これらの商標は、単なるブランドネームを超えて、日本の食文化を守り、発展させる重要な役割を担っているといえるでしょう。
サバの生産量減少という厳しい現実に直面しながらも、創意工夫によって新たな価値を生み出す取り組みは、今後の日本の水産業にとって重要な示唆を与えています。商標登録の観点から見ても、これらの事例は、地域資源の活用や伝統食材の現代的アレンジという、ブランディングの取り組みとして注目に値します。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247