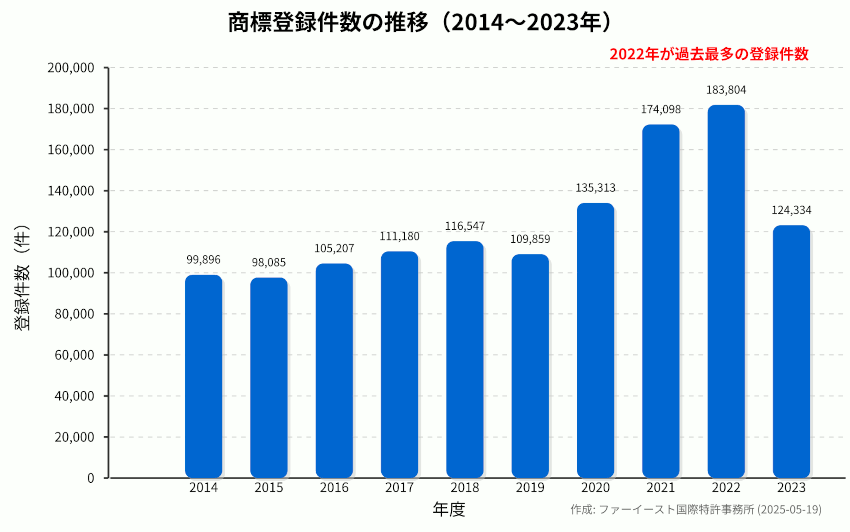索 引
1. はじめに
知的財産戦略の要となる商標登録。近年のデジタル化やグローバル展開の加速により、その重要性は高まっています。本記事では、特許庁が公開した2024年版年次報告書のデータを基に、過去10年間(2014年〜2023年)の商標出願・登録状況を徹底分析します。
単なる数字の羅列ではなく、その背景にある企業動向や社会情勢との関連性まで掘り下げ、これからのブランド保護戦略に役立つ知見をお届けします。
2. 出願件数の推移:2017年をピークとした山型カーブ
商標出願件数の10年間の推移を見ると、明確な「山型」のトレンドが浮かび上がります。
2014年にはおよそ12万4千件だった出願件数は、2017年に約19万件と過去10年間のピークを迎えました。
この急増期は、いわゆる横取り出願といわれる、特許庁の印紙代を支払わずに次々と出願を繰り返す行為の影響が大きいです。ちょっとしたミスを理由に、直ちに商標登録出願が却下されない出願人の保護措置が逆手に取られた形です。
その後、特許庁からの措置等が効果を出し始め、2018年以降は緩やかな減少傾向に転じ、2023年には約16万4千件まで落ち込んでいます。
また2022年から2023年にかけては約6,000件の減少が見られました。このような減少傾向は、コロナ禍での事業活動の停滞や、新規ビジネス立ち上げの減速が影響していると考えられます。また、すでに多くの分野で商標登録が飽和状態となり、新たな出願の余地が狭まっていることも一因かもしれません。
3. 登録件数の推移:出願増加から約3〜4年遅れで波及
商標の登録件数は出願件数とは異なるカーブを描いています。
2014年に約10万件だった登録件数は、出願件数の増加に連動する形で徐々に増加し、2021年には約17万4千件と過去10年間の最高値を記録しました。注目すべきは、出願件数のピークが2017年であるのに対し、登録件数のピークは4年後の2021年となっている点です。これは、出願するだけで実際には登録手続まで進まないみせかけ出願が減少した結果を反映しています。
2022年には約18万3千件と高水準を維持したものの、2023年には約12万4千件まで急減しました。
この減少は単に出願件数の減少を反映しているだけでなく、審査体制や審査方針の変化も関係している可能性があります。
4. ファーストアクション(初動審査)件数:審査の「加速と減速」
「ファーストアクション」(初回の審査結果通知)は、商標審査のスピードを測る重要な指標です。
2014年に約12万2千件だったファーストアクション件数は、2021年には約21万3千件と飛躍的に増加しました。
この急増は、特許庁が推進した「審査迅速化アクションプラン」の成果と言えるでしょう。AI技術の活用や審査プロセスの効率化により、審査のスピードが大幅に向上した時期と重なります。
5. 登録査定件数:質の変化が数字に表れる
登録査定件数(審査を経て「登録可」と判断された件数)も、興味深い変動を示しています。
2014年の約10万5千件から、2022年には約18万8千件とほぼ倍増しました。特に2020年から2022年にかけての急増は、審査官の増員や審査プロセスの効率化が功を奏した結果と考えられます。
しかし、2023年には約12万6千件と大幅に減少しています。
この減少は、出願内容自体の質が変化している可能性を示唆しています。
具体的には、商標登録出願はしてみたものの、事業環境の急激な変化により登録をあきらめる件数が増えた等の要因が考えられます。
また、特許庁の審査基準がより厳格になり、以前なら登録可能だった商標が拒絶されるケースが増えていることも考えられます。
6. 審査期間の変化:迅速化と品質のバランス
数字に表れていないものの、出願から登録までの期間にも変化が見られます。
2010年代前半には出願から登録までの期間が平均して12〜18ヶ月程度だったのに対し、2020年代に入ると約8〜10ヶ月程度まで短縮されました。これは先述の審査迅速化の取り組みの成果です。しかし、2023年のファーストアクション件数の減少を考えると、今後は再び審査期間が長期化する可能性があります。
企業のブランド戦略においては、この審査期間の変動を考慮に入れた計画が重要になってきます。特に新製品やサービスの発表時期に合わせた商標取得を目指す場合、余裕を持った出願スケジュールが必要となるでしょう。
7. 分野別の出願傾向:デジタル領域の拡大
10年間の統計を業種別に分析すると、特に成長している分野が見えてきます。
2014年時点では、日用品や飲食料品関連の商標出願が最も多かったのに対し、2023年にはデジタルサービス、オンラインコンテンツ、フィンテック関連の出願が急増しています。特に第9類(コンピュータソフトウェア等)、第35類(広告・ビジネス)、第42類(科学技術サービス)での出願増加が顕著です。
これは社会全体のデジタル化の進展を反映した結果であり、今後もこの傾向は続くと予想されます。特にメタバースやNFT関連の商標出願は2021年以降急増しており、新しいビジネス領域における知的財産保護の重要性が高まっています。
8. 外国人による出願の増加:グローバル競争の激化
もう一つの注目すべき変化は、外国企業による日本での商標出願の増加です。
2014年には外国人による登録は全体の約20%でしたが、2023年には約27%まで増加しています。特に中国企業からの出願が急増しており、その背景には越境ECの普及や、中国企業の日本市場への参入拡大があります。
この傾向は日本企業にとって、国内市場でのブランド保護競争が激化していることを意味します。自社のブランドを守るためには、予防的な出願戦略や、商標モニタリングの強化が不可欠となっています。
9. 年度別まとめ表(2014〜2023年)
| 年度 | 出願件数 | ファーストアクション | 登録査定 | 登録件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 124,442 | 122,048 | 105,637 | 99,896 |
| 2015 | 147,283 | 111,831 | 100,244 | 98,085 |
| 2016 | 161,859 | 131,624 | 113,025 | 105,207 |
| 2017 | 190,939 | 126,407 | 115,754 | 111,180 |
| 2018 | 184,483 | 137,463 | 119,610 | 116,547 |
| 2019 | 190,773 | 134,834 | 117,186 | 109,859 |
| 2020 | 181,072 | 172,931 | 146,708 | 135,313 |
| 2021 | 184,631 | 213,224 | 185,415 | 174,098 |
| 2022 | 170,275 | 208,740 | 188,157 | 183,804 |
| 2023 | 164,061 | 142,461 | 125,973 | 124,334 |
【出典:特許行政年次報告書2024年版 71ページ】
10. これからの商標戦略に求められるもの
10年間のトレンド分析から見えてくる、これからの商標戦略のポイントをお伝えします。
1. 先を見据えた計画的な出願
審査処理速度の変動を考慮すると、重要なブランドについては余裕を持った出願計画が不可欠です。特に事業の柱となるブランドについては、使用開始の1年以上前からの出願準備が望ましいでしょう。また、出願が集中する時期(年度末など)を避けることで、比較的スムーズな審査が期待できます。
2. 広い権利範囲の確保
近年は商標の類似性判断が厳格化する傾向にあります。そのため、中核となるブランドについては、周辺領域も含めた包括的な保護戦略が重要です。具体的には、類似の表記や称呼をカバーする複数の商標出願や、将来的な事業展開を見据えた区分の選定などが効果的です。
3. 国際的な視点での権利取得
外国企業による日本での出願増加は、裏を返せば日本企業も海外での商標保護を強化すべきことを示唆しています。特に中国市場では、現地企業による日本ブランドの「先取り出願」リスクが高まっているため、進出予定を見据えて予防的な出願を検討する価値があります。
4. デジタル領域での積極的な保護
メタバース、NFT、Web3.0など、新しいデジタル領域での商標保護の重要性が高まっています。
従来のビジネスモデルにとらわれず、将来的なデジタル展開を見据えた商標戦略が求められます。特に第9類、第35類、第42類での権利確保は、将来の事業展開の自由度を高めることにつながります。
11. おわりに
商標は企業の知的財産戦略の要です。過去10年間の出願・登録データから見えてくるトレンドは、日本の産業構造の変化や、グローバル競争の激化を如実に反映しています。
特に2021〜2022年にかけて審査処理が高速化した一方、2023年にはその反動とも取れる処理件数の減少が見られました。この変動は今後も続く可能性があり、企業は柔軟な対応が求められます。
ブランドの価値を守るためには、データに基づいた出願タイミングの選定と、長期的視点での登録戦略がますます重要になるでしょう。自社のビジネスモデルや市場環境に合わせた、オーダーメイドの商標戦略の構築が成功の鍵となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘