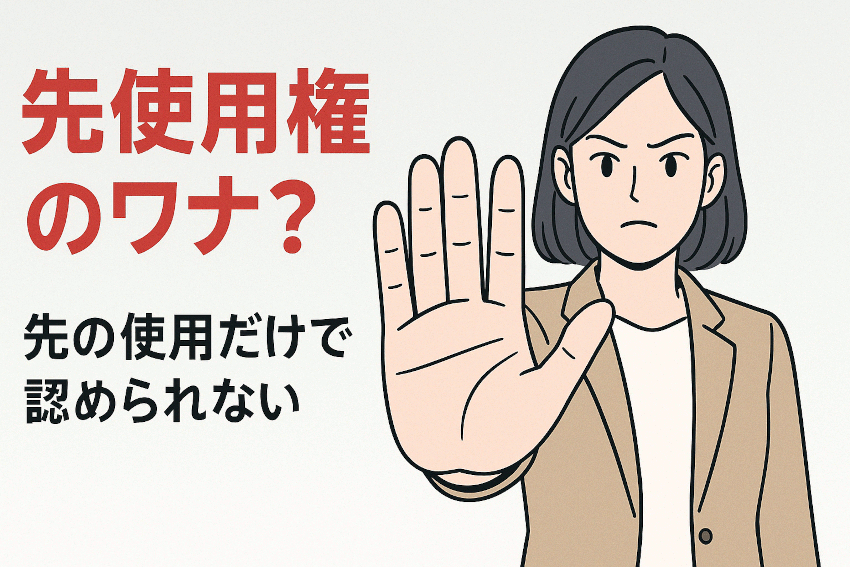索 引
商標権侵害を疑われた場合は、「先使用権」は口に出してはいけません。商標権侵害の事実がないなら、先使用権を主張するまでもないです。
「先使用権」を口にする、ということは、逆に商標権侵害の事実があったことを認めたことにもなりかねません。ここを理解した上で、以下の説明をお聞きください。
こんにちは、弁理士の平野泰弘です。今回は「先使用権」という、商標実務において意外と知られていない権利についてご説明します。
商標登録をお考えの方や、すでに商標を使用している方にとって重要な知識となりますので、ぜひ最後までお読みください。
1. 先使用権の基本概念
日本の商標制度は「先願主義」、つまり「早い者勝ち」が原則です。通常、他人が先に商標登録出願をすれば、たとえあなたが先に使っていたとしても、その商標を使い続けることができなくなってしまいます。
しかし、ビジネスの現場では「以前から使っている看板やブランド名を突然使えなくなる」という事態は避けたいもの。
そこで商標法は、一定の条件を満たす場合に限り、先に使用していた人にも商標の継続使用を認める「先使用権」という制度を設けています。
先使用権とは具体的に、他人が商標出願するより前から使用していた未登録商標が需要者(お客様など)の間で周知となっている場合に、その後他人が商標登録しても、従前の使用範囲で継続して使用できる権利のことです。
つまり、商標権者であっても先使用権者の使用を差し止めることはできないのです。
また先使用権は、裁判の中で認められる抗弁権の一種で、裁判所で認定されてはじめてその範囲や効力が認められます。最初から存在する権利ではない点にもご注意ください。
2. 先使用権が認められるための6つの条件
先使用権は誰でも主張できるわけではありません。以下の6つの条件をすべて満たす必要があります(商標法第32条)。
強調しますが、他人が出願登録する前から、自分は商標を使っていた、というだけでは先使用権は認められません。ここが盲点になります。
2-1. 商標の継続使用開始時期
他人の商標登録出願日よりも前に、その商標の使用を開始していること。出願日までの使用実績が重要となります。
2-2. 日本国内での使用
当該商標を日本国内において使用していること。海外での使用のみでは、日本における先使用権は認められません。
2-3. 不正の目的がないこと
商標を使用する目的が、他人に対する不正競争を目的としたものでないこと。他人の商標の価値にただ乗りしようとする意図がある場合は認められません。
2-4. 商標および商品・役務の同一性・類似性
先使用者が使用している商標が、他人の出願商標と同一または類似であり、かつその使用対象である商品・サービスも同一または類似の範囲内であること。まったく異なる商品・サービスでの使用では主張できません。
2-5. 需要者間の周知性
他人の商標出願時に、先使用者の使用商標が自己の取り扱う商品・役務を示すものとして需要者の間に広く認識されていること。
これが最も重要かつ立証が難しい要件です。単に「先に使っていた」だけでは不十分で、その商標が一定の範囲で知られていることが必要です。
上記の条件を全て満たして、はじめて商標登録の先使用権が認められます。
なお、「需要者の間に広く認識」の基準は、商標法第4条第1項第10号(周知商標の登録禁止規定)の場合よりは緩やかで、全国的でなく一地方で認知されていれば足りると解されています。ただし、地域的範囲の具体的な基準は裁判例によって異なります。
また、地域団体商標に関しては特例があり、商標法第32条の2では周知性は要件とされておらず、出願前から善意で使用していた者であれば周知でなくとも先使用権が認められます。
2-6. 継続して使用していること
出願時から現在まで、先使用商標を同一の範囲内で継続的に使用していること。営業の一時的中断など正当な理由がある場合を除き、使用を中断していないことが求められます。
3. 先使用権を主張するための立証方法
先使用権を主張する際には、先述の要件を充足する事実を自ら立証する必要があります。1個でも要件が欠けると先使用権は認められません。厳しい条件が課せられているのが分かると思います。
これは容易なことではありません。特に「需要者の間に広く認識されていること(周知性)」の立証ハードルは高く、単一の証拠だけで足りるものではないのです。
3-1. 立証責任の所在と難易度
先使用権を主張する側が、すべての要件を立証する責任を負います。この立証に失敗すると、先使用権は認められず商標権侵害が成立してしまうため注意が必要です。あらゆる観点から証拠資料を徹底的に収集し、継続的かつ広範な使用実績を示す必要があります。
3-2. 立証に必要な証拠資料
先使用権を主張する際には、以下のような資料を準備し、客観的な証拠として提示することが求められます:
3-3. 商標の使用実態に関する資料
実際に使用している商標の態様(ロゴや表示)およびその商標を付した商品・役務の現物や写真など、商標の使用事実を裏付けるものを用意しましょう。
3-4. 使用開始時期・期間の資料
当該商標の使用開始時期およびその後の使用期間を裏付ける証拠が必要です。初出時の広告物・注文書・日付の入った記録やファイル、タイムスタンプのあるデータなどが有効です。
3-5. 使用地域に関する資料
商標を使用している地域的範囲を示すものとして、販売・提供エリアが分かる領収書や配送伝票、店舗の所在一覧、ウェブサイトの流入解析などがあります。
3-6. 取引規模に関する資料
商標を使用した商品の販売数量・売上高、提供したサービスの顧客数、直営店・取扱店の店舗数など、営業規模を裏付けるデータを集めましょう。
3-7. 広告・宣伝実績の資料
当該商標について行った広告宣伝の方法・回数・内容・地域を示すものとして、広告に投下した費用額、実際の広告物やチラシ、広告掲載誌面、Webサイトのアクセス数・SNSのフォロワー数等が重要です。
3-8. 社会的評価を示す資料
商標や商品・サービスがメディアで取り上げられた実績や顧客の認知度を示すものとして、新聞・雑誌記事、テレビ・ネットニュースの掲載記録、第三者のレビューや顧客アンケート結果なども有効な証拠となります。
3-9. 証拠保全の工夫
日頃から自社の商標使用実績を記録・保存しておくことが肝要です。例えば、以下のような対策が考えられます:
- 使用中のパッケージや広告物を公証役場で確定日付付の私署証書として保管する
- デジタルデータに電子署名やタイムスタンプを付与して信頼性を確保しておく
先使用権の主張は事後の立証コストが大きいため、商標の継続使用が見込まれる場合は早めに商標登録出願を検討することも重要です。
4. 先使用権をめぐる実際の事例
先使用権が認められるか否かは、具体的な事案によって判断が分かれます。以下に、裁判例を見てみましょう。
4-1. 先使用権が認められた例:「ケンちゃん餃子」事件
平成19年(ワ)第3083号の大阪地裁平成21年3月26日判決では、餃子製造販売業者である原告が、関東及び甲信越地方を中心に展開してきた「ケンちゃん餃子」の標章について先使用権を有することの確認を求めました。
裁判では、原告の商標使用開始(昭和年代からの販売開始)から他人出願時までの販売地域・売上高・工場規模・宣伝広告(ラジオCM等)に関する豊富な証拠が提出されました。
その結果、「ケンちゃん餃子」は首都圏および甲信越の1都11県において周知と認められ、これらの地域で先使用権の成立が肯定されました。
この事例では、商標出願時点(平成8年)から約10年以上前に遡って周知性を立証する大変さも指摘されています。しかし、充実した証拠資料の提出により先使用権が認められた事例です。
4-2. 先使用権が否定された例①:美容室「aise/cache」事件
大阪地裁平成24年(ワ)第6896号判決では、美容サロンが同一市内で使用してきた「aise/cache」の商標について、需要者の間の認識が一部地域に留まるとして周知性を満たさないと判断されました。
裁判所は「先使用権によって商標権の効力が全国で制限される重大性」に鑑み、少なくとも同一市や隣接市町村といった一定の地域範囲で需要者に認識されている必要があると判示し、当該ケースではその要件を充足しないとして先使用権を認めていません。
4-3. 先使用権が否定された例②:葬祭ホール「久宝殿」事件
大阪地裁令和5年11月30日判決では、葬儀サービス業者Y社は自社の標章「久宝殿」が先使用により継続使用できると主張しました。Y社は大阪府東大阪市の葬儀会館で約20年にわたり当該標章を使用していましたが、裁判所は「需要者の間に広く認識されていた」とは認められないとしてY社の先使用権を否定し、商標権者X社による使用差止請求を認容しました。
Y社は葬儀業の商圏が半径2km程度であると主張しましたが、裁判所は検討範囲をそれより広い東大阪市および隣接する八尾市全域(最大半径約10km)に設定してなお周知性が立証不足であると判断しています。
5. まとめ:先使用権は「保険」ではなく「最終手段」
先使用権が認められるか否かの判断はケースバイケースであり、明確な基準を予め示すことは困難です。過去の裁判例でも、周知性が肯定された地域的・時間的範囲は事案により様々で、一律には語れません。
一般的に、先使用権の主張は証明すべき要件が多く証拠集めも困難なため、実務上は「まず商標登録を行って権利化しておく」ことが最善策と言えるでしょう。先使用権はあくまで非常手段であり、平時から以下の対応を心がけることをお勧めします:
- 1. 使用している商標は早めに登録出願する
- 2. 商標使用の証拠(広告、販売実績など)を日常的に保存する
- 3. 商標の使用範囲(地域・商品・サービス)を明確に記録しておく
- 4. 商標使用の周知性を高める努力を継続する
上記の対策を講じておくことで、万が一のときに先使用権を主張できる可能性が高まりますし、そもそも他人に先に出願されるリスクも減らせるでしょう。
皆様のビジネスが商標トラブルに巻き込まれないよう、日頃の備えを大切にしてください。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247