索 引
1. 導入──あの「PPAP」が再び注目される理由
[これまでの経緯]PPAPの商標が他人に商標登録出願された問題の解説
[※注意]:本稿で取り上げるPPAPはメールへの文書添付方法ではありません。ピコ太郎です。ご注意ください。
2016年、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」が世界中で大ブームとなりました。
あれから約10年が経過した2025年の今、この「PPAP」が再び話題になっています。今回は懐かしのヒット曲としてではなく、日本の商標制度における重要な教訓として注目を集めているのです。
当時「PPAP」の爆発的人気に乗じて第三者企業が商標を出願するという「横取り騒動」が発生しました。
この出来事は、瞬く間に広がるインターネット上のトレンドと知的財産権保護の狭間で生じる問題を浮き彫りにしました。
10年経った今でも、この事件は多くのスタートアップや中小企業にとって、自社ブランドを守るための重要な教訓となっています。
デジタル時代において、バイラルヒットの商業価値は計り知れません。
しかし、そのブランド価値を法的に保護する体制が整わないうちに第三者に権利を奪われてしまうリスクも同時に高まっています。
特に2025年の現在では、生成AI技術の発展により新しいコンテンツやブランド名が次々と生まれる時代となり、この「横取り問題」はより身近なリスクとして認識すべき課題となっているのです。
2. 社会現象から一転、”横取り出願”が発覚するまで
2016年8月、ピコ太郎こと古坂大魔王氏が演じるキャラクターによる「PPAP」動画がYouTubeで公開されました。わずか1分程度の短い動画は瞬く間に世界中に広まり、ジャスティン・ビーバーのSNS投稿をきっかけに爆発的な人気を獲得。グローバルチャートにも入るヒットとなり、日本発のコンテンツとして大きな注目を集めました。
この社会現象が広がりを見せる中、2016年10月5日、株式会社ベストライセンスという企業が「PPAP」の商標を特許庁に出願したことが明らかになりました。
この出願は第9類(コンピュータソフトウェアなど)、第41類(教育・娯楽など)を含む複数の区分にわたるものでした。
この事実が報道されるとすぐに、SNSを中心に大きな反発が巻き起こりました。
「権利者でない第三者が便乗して出願するのは不当ではないか」「本来の創作者の権利を侵害している」といった批判が相次ぎました。
一方で、商標制度は基本的に「先願主義」であり、早く出願した者が権利を得られるという制度的側面もあり、議論は複雑化しました。
エイベックス・マネジメント株式会社(ピコ太郎の所属事務所側)も後追いで商標出願を行いましたが、既に出願されていた区分については後れを取る形となりました。
この出来事は、バイラルコンテンツの権利保護がいかに難しいかを示す象徴的な事例となったのです。
3. 年表でたどる 2016 – 2025——事件の全タイムライン
PPAP商標横取り事件の推移年表
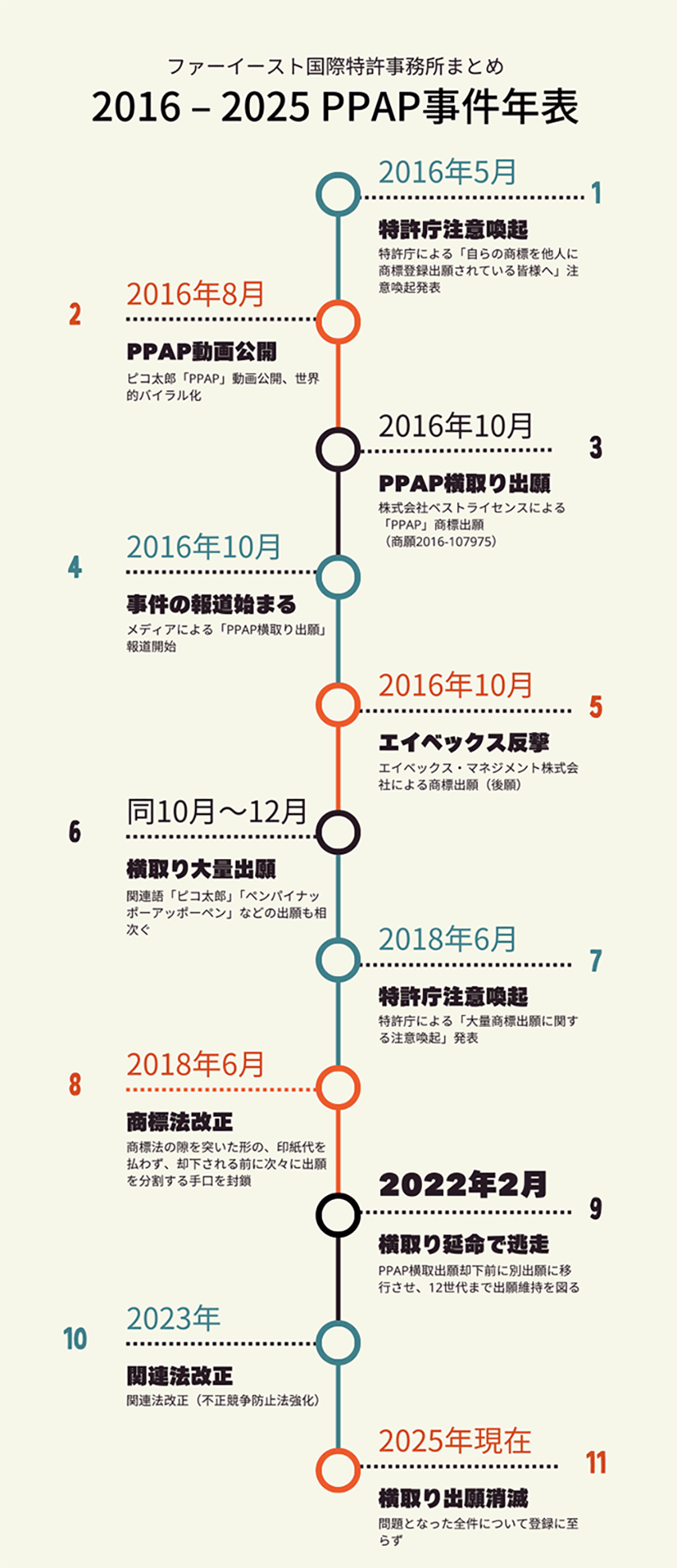
PPAPの商標騒動から現在までの流れを時系列で追ってみましょう。この10年間で、制度自体や企業の対応にも大きな変化がありました。
- 2016年5月:特許庁による「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ」注意喚起発表
- 2016年8月:ピコ太郎「PPAP」動画公開、世界的バイラル化
- 2016年10月:株式会社ベストライセンスによる「PPAP」商標出願(商願2016-107975)
- 2016年10月:メディアによる「PPAP横取り出願」報道開始
- 2016年10月:エイベックス・マネジメント株式会社による商標出願(後願)
- 2016年10月〜12月:関連語「ピコ太郎」「ペンパイナッポーアッポーペン」などの出願も相次ぐ
- 2018年6月:商標法改正(分割出願の規制強化)
- 2018年6月:特許庁による「大量商標出願に関する注意喚起」発表
- 2022年8月:ベストライセンス側はPPAP横取出願却下前に別出願に移行させ、12世代まで出願維持を図る
- 2023年:関連法改正(不正競争防止法強化)
- 2025年現在:問題となった全件について登録に至らず
この一連の流れから見えてくるのは、制度上の問題点と、それに対応するための法改正の動きです。
特に2018年の商標法改正では、この事件を受けて分割出願を利用した出願却下前に、別出願に移行させて延命を図る権利取得の抑制による「出願乱発」の防止策が導入されました。
4. 冒認(ぼうにん)出願とは何か──日本の商標制度を読み解く
PPAPの事例で問題となった「冒認出願」とは、本来の権利者ではない第三者が、他人の商標を無断で出願する行為を指します。
日本の商標制度は基本的に「先願主義」と「登録主義」を採用しており、原則として最初に出願した者に権利が与えられる仕組みになっています。
先願主義は、誰が特許庁に願書を先に提出したかが明らかですので、後から本当の権利者を名乗る第三者が、次々と現れることを防止できる利点があります。
一方で、商標法にはこうした「横取り」を防ぐための規定も存在します。
一連の大量出願では、ベストライセンス社側は、特許庁に出願維持のための費用を一切納入しなかったため、最終的に権利取得までには至りませんでした。
先に出願した者を保護する先願主義は、誰が本当の権利者かの争いを防ぐ意味で意義があります。
一方で、ベストライセンス社の代表は、元・弁理士であり、商標法の裏の裏まで知り尽くしています。出願の際に特許庁に出願手数料を支払わず、料金不納により出願が却下される前に別出願に乗り換える分割出願を繰り返しました。
これは、善意の出願を原則として想定している法律の制度的な保護が追いつかないケースの一つでもあります。出願に費用納入不備があっても直ちには却下されない救済制度の裏を突かれた形です。PPAP騒動はまさにこの「救済制度の隙を突いて横取りが起きる」という構造的ギャップを露呈させた事例だったのです。
さらに、日本の商標制度では基本的に審査官による職権審査が行われますが、すべての事例について出願者が、横取りの事実を隠した上で特許庁に権利請求した場合には、正当な権利者かどうかを現実に調査することは現実的に難しい面もあります。
そのため、問題のある出願についても一定数が審査を通過してしまう可能性があるのです。
5. 特許庁の公式対応と法改正が残したもの
PPAP騒動を契機として、特許庁や立法府は商標制度に関するいくつかの重要な対応を行いました。
2018年の商標法改正では、PPAPのケースで問題となった「分割出願の濫用」に対する規制が強化されました。
分割出願とは、一つの商標出願を複数に分けることができる制度ですが、この制度を利用して、出願料金を払わないことを理由として出願が却下される前に、次々に別の出願に乗り換えることができる、多数の出願を生み出す手法が問題視されていました。
改正後は分割出願に対しても元の出願と同額の印紙代が必要となり、経済的コストが高まることで濫用的な利用の抑制が図られました。
また、2018年6月に特許庁から「大量商標出願に関する注意喚起」が発表されました。
この文書では、分割出願を悪用した場合には、他者の出願に影響を与えないことが明確に示されています。結果的に、商標の権利取得を目的としない出願や、不正な目的での分割出願に対して厳格に対処されることになります。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で各出願の経過を追ってみると、PPAP関連の出願は最終的にすべて登録に至らなかったことがわかります。
この一連の対応は、日本の商標制度が持つ問題点をあぶり出した例として評価できますが、同時に事前予防の難しさも浮き彫りにしています。
制度的には問題のある出願を排除できる仕組みはありつつも、そのプロセスには時間とコストがかかり、本来の権利者が負担を強いられる点は今後も課題として残されています。
6. 同一出願人が狙った他の流行語 ─ 横取りはPPAPだけではない
PPAP騒動の出願人である企業は、これ以外にも当時流行していた言葉やフレーズの商標出願を多数行っていたことが明らかになっています。
「恋ダンス」(2016年のドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のエンディングダンス)、「インスタ映え」(2017年流行語大賞)、など、その時々の流行語やトレンドを次々と出願していました。
これらの出願データを分析すると、特定の企業による「流行語の先取り出願」が一時期に集中していることがわかります。
2016年から2018年にかけては年間数万件の大量の出願があった一方で、特許庁の厳格化方針が明確になった2020年以降は減少し、2025年現在では年間数百件程度に減少しています。
こうした変化は、制度的な対応が一定の効果を上げていることを示していますが、同時に流行に乗じた出願行動自体は無くなっておらず、形を変えて続いているという現実も見逃せません。
特に、一般名称や業界用語を組み合わせた商標や、AIが生成した新造語などへの出願シフトが見られます。企業としては、常に最新の出願動向を把握し、自社ブランドの保護策を講じる必要があるでしょう。
7. ピコ太郎/エイベックスの”炎上後ブランディング”
PPAP騒動を経験したピコ太郎陣営(エイベックス・マネジメント)はその後、権利維持に努めています。
国際的な商標保護の強化も図っています。日本国内外で「PPAP」関連の権利を確保しました。
取られる前に先に権利を確保する国内のブランディング戦略の転換は、「炎上」を逆手にとった例として評価できます。商標トラブルという危機を、むしろ正規品の価値を高める機会に変えたのです。
このケースは、知的財産権トラブル後の信頼回復戦略として、多くの企業が参考にすべき事例と言えるでしょう。問題を隠すのではなく、むしろ積極的に「正規品」であることをアピールし、消費者との信頼関係を再構築する道筋を示しています。
8. いま企業が取るべき5つの実務アクション
PPAP騒動から学び、2025年の現在、企業が自社ブランドを守るために取るべき具体的なアクションを5つご紹介します。
1. 流行語・新サービス公開前の仮出願
新しいサービス名やキャッチフレーズを考案した段階で、公開前に仮出願を行うことを検討しましょう。
特に話題性を狙ったマーケティング施策を展開する際は、SNSでのバイラル拡散前に権利確保の手続きを進めておくことが重要です。商標の仮出願は費用も比較的抑えられるため、複数の候補を出願しておくという選択肢も現実的です。
2. 国内外ウォッチングサービスの活用
自社ブランドに関連する商標出願を定期的に監視する「ウォッチングサービス」の活用を検討してください。
ただし、特許庁に申請しなければ商標権は得られません。他人に取られると、通常その解決費用は出願費用を上回ります。実際に特許庁に商標を出願した後は、先願主義により後からの出願による権利取得をシャットアウトできます。ウオッチサービスを利用する費用を考慮すると、実際に特許庁に商標登録出願をするのが安上がりになる場合もあります。
3. 異議申立て・無効審判の初動と証拠準備
万が一、第三者による権利の「横取り」が発生した場合に備え、異議申立てや無効審判請求のための証拠収集体制を整えておきましょう。
特に重要なのは、自社商標の「使用証拠」と「周知性を示す証拠」です。
SNS上での言及、メディア掲載履歴、販売実績などを日頃からデータベース化しておくことで、いざという時の対応力が大きく変わります。
4. 生成 AI 時代の「スピード出願」体制づくり
生成AI技術の発達により、新しいアイデアやコンセプトが生まれるスピードは加速しています。この環境下では、発想から出願までの時間短縮が鍵となります。社内に「商標検討委員会」のような体制を整え、新サービスやキャンペーン名の検討段階から知財部門を関与させることで、スピーディーな出願判断が可能になります。
5. 弁理士への早期相談 ─ 費用感と ROI
商標戦略に不安がある場合は、専門家である弁理士への相談を検討してください。
特に創業間もない企業では「コストがかかるから後回し」という判断をしがちですが、トラブル発生後の対応コストと比較すれば、予防的な相談費用ははるかに小さいものです。
2025年現在では、特許事務所も増えています。最初から弁理士・弁護士と相談することは、後からの横取り対策費の発生を防止する上で、費用対効果の高い投資と言えるでしょう。
9. まとめ ─ ”10 年前の事件”を他山の石に
PPAP商標横取り騒動から約10年が経過した2025年の今、この事件が残した教訓は色あせるどころか、むしろその重要性を増しています。デジタル時代のブランド価値はかつてないほど高まり、同時に権利の「横取り」リスクも拡大しているからです。
特に生成AIの発展により、新しいコンテンツやブランド名が次々と生み出される現在においては、「先に思いついた」だけでは権利は守れません。法的保護の仕組みを理解し、積極的に活用していくことが不可欠です。
制度面でも、2018年の商標法改正や特許庁による注意喚起など、対策は進んできました。しかし、これらの制度的保護はあくまで「事後的」なものであり、発生した問題を解決する助けにはなっても、トラブルそのものを完全に予防できるわけではありません。
企業としては「自分たちのブランドは自分たちで守る」という意識を持ち、商標出願を経営戦略の一部として位置づけることが重要です。特にスタートアップや成長途上の中小企業にとって、ブランド資産は将来的な企業価値を大きく左右する要素となります。
10年前のPPAP騒動を他山の石として、これからのビジネス展開に活かしていきましょう。知的財産権保護は決して大企業だけの課題ではなく、あらゆる規模の企業にとって、持続可能な成長のための必須要素なのです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
- J-PlatPat
- 特許庁「大量商標出願に関する注意喚起」(2020/02/10公開)
- 商標法平成30年改正概要(経産省資料)
- 「PPAP商標出願騒動の全容」(日本経済新聞、2016年10月)
- 「商標制度から見る冒認出願問題」(知財管理、2021年3月号)
- 「デジタル時代の知的財産戦略」(商事法務、2023年)

