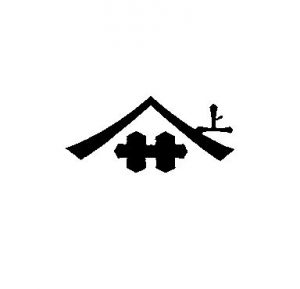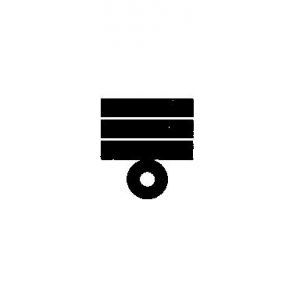1. これらの商標に見覚えがありますか?
私たちの食卓には、実にさまざまな商品が並んでいます。そして、それらの商品には必ずといってよいほど商標が付けられています。今回は、皆さんが普段から目にしている身近な商標について、クイズ形式でご紹介します。
以下に示す商標がどのような商品に付けられているか、少しだけ考えてみてください。きっと普段、食卓で使っている方も多いのではないでしょうか。
Q1:多角形が印象的な商標は、どのメーカーのものでしょうか?
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
六角形の形には深い意味があります。この形状の別の呼び方から連想してみると、答えが見えてくるかもしれません。
Q2:「上」の文字は江戸時代からの誇り。この商標は、どのメーカーのものでしょうか?
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
商標の上部には「山」を表す図形があります。これらの要素を組み合わせた名前を考えてみると、答えにたどり着けるでしょう。
Q3:3本の線が特徴的な商標は、どのメーカーのものでしょうか?
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
円を表す漢字にはいくつかの種類があります。その中から、3本の線と組み合わせることで意味を持つ言葉を探してみてください。
2. 実は、こんな商品に使われています
A1:野田の醸造家たちが結集した老舗醤油メーカー
正解は、キッコーマンです。
日本の醤油メーカーとして広く知られているキッコーマンの商品は、多くの家庭で使われています。このメーカーの歴史と商標に込められた思いには、興味深い背景があります。
キッコーマンの歴史は江戸時代初期にさかのぼります。
現在の千葉県野田市で醤油づくりが始められたのがその始まりです。野田は原料となる大豆や小麦などが手に入りやすく、江戸への運搬も便利だったため、醤油の一大産地として発展しました。
醤油のふるさととも呼ばれるこの地で、長い年月をかけて技術が磨かれていきました。
1917年には「野田醤油株式会社」が設立されます。
これは野田の醸造家一族が合同でつくった会社で、それぞれの家に伝わる秘伝の技や技術を結集させました。
高品質な醤油づくりを目指したこの取り組みは、当時としては画期的なものでした。
設立当初は、それぞれの家が受け継いできた醤油の商標が200以上存在していました。その後、これらを段階的に統合していき、1927年には東京市場で、1940年には全国でキッコーマンという名称に統一されました。
六角形のなかに「萬」の文字が描かれたキッコーマンのマークは、明治時代に商標登録されています。
1911年8月15日に出願され、1912年1月19日に登録が完了しました。
この六角形は亀の甲羅、つまり「亀甲」を表しています。「萬」の文字と合わせて「亀甲萬」という名称を表現しています。現在では「キッコーマン」や「kikkoman」というカタカナや英字の表記が一般的ですが、「亀甲萬」という漢字表記も商標として登録されています。
この六角形の「亀甲」を表すマークは、千葉県香取市にある香取神宮に由来するものです。
香取神宮は千葉県の旧国名である下総国で格式が高い一宮であり、全国に約400ある香取神社の総本社です。正式名称は「下総国亀甲山香取神宮」といいます。
山号である「亀甲」と、神宝の「三盛亀甲紋松鶴鏡」の裏面に描かれた亀甲文様を元に六角形が描かれました。さらに「亀は萬歳の仙齢を有する」という故事から、「萬」の字が記されたと伝えられています。
A2:「最上醤油」の称号を得た醤油メーカー
正解は、ヤマサ醤油です。
ヤマサ醤油は、代々受け継いできた独自の麹菌「ヤマサ菌」に改良を重ね、独特の色や味、香り、風味のよさを実現しています。
一般家庭だけでなく、高級日本料理店でも使われている醤油です。現在はメインとなる醤油のほか、昆布ぽん酢や昆布つゆなどの商品でも知られています。
創業は1645年、江戸幕府が開かれてから約40年たった頃のことです。醤油発祥の地といわれる紀州出身である初代濱口儀兵衛が、現在の千葉県銚子市に渡って商いを始めました。
銚子は穏やかな気候と高い湿度で醤油づくりに適した土地であり、漁業とともに醤油の街として発展していきます。
「濱口儀兵衛商店」(当時)は江戸の繁栄に合わせるように発展していき、明治時代の1895年には関東で最初の宮内省(現在の宮内庁)御用達醤油に選ばれました。
その後、1928年に「濱口儀兵衛商店」から現在の社名である「ヤマサ醤油株式会社」に変更されます。当時は創業者の名前や地名を社名に使うことが多く、商品名を社名にするのは珍しい例でした。
ヤマサ醤油の商標には、山笠の右上に「上」の文字が書かれています。この文字には重要な意味があります。江戸時代、品質の優れた醤油には幕府から「最上醤油」の称号が与えられました。
ヤマサ醤油は1864年にこの栄誉を獲得しています。その証となるのが、この「上」の文字です。高い品質の商品をつくり続けるという決意を込めて、現在でも商標に「上」の文字を記し続けています。
東京・浅草の浅草寺宝物殿には、「商標感得の図」という絵画が保管されています。これは明治中期の洋画家である高橋源吉が描いたもので、商標の付いた醤油樽と文机で思案する女性の姿が描かれています。ヤマサ醤油の商標の由来には、夢枕に立った観音さまによって授けられたという説もあるそうです。
この絵画は1894年に奉納され、現在では年に1度だけ公開されています。どのような絵であるかは、ヤマサ醤油のホームページ(https://www.yamasa.com/enjoy/history/dataroom/)でも確認できます。
A3:家紋から生まれたシンプルで特徴的な商標
正解は、ミツカンです。
ミツカンは、日本の代表的な酢のメーカーとして知られています。
1804年に創業したミツカンの歴史は、酒造業を営んでいた初代中野又左衛門が粕酢づくりに成功したことから始まります。酒粕を原料とした粕酢は握りずしに合うと、江戸で評判になりました。
初代のフロンティア精神は代々受け継がれていきました。酢の製造を行う一方で、1900年にはパリ万博で金賞を受賞した「カブトビール」を製造しています。
時代が昭和や平成に移った後も、1964年には「味ぽん」、1982年には「おむすび山」、1998年には納豆「金のつぶ」シリーズを発売するなど、酢以外のさまざまな商品も手がけています。
ミツカンの商標は、4代目中埜又左衛門によって考案されました。きっかけとなったのは、1884年に制定された商標条例です。この条例により、自身の商標を独占的に使用するためには、出願・登録が必要となりました。
当初、又左衛門が登録を願い出ていたのは「勘」の文字を○で囲んだ「丸勘」という商標でした。しかし、これは当時多くの酢屋で使われており、3日ほど早く名古屋の酢屋によって出願されていました。そのため、又左衛門は新たな商標を考える必要に迫られます。
悩んだ末に、○のなかに三本の線を描いた中埜家の家紋を元にした商標を思いつきました。三本線の下に○(=「環」)をつけ、「三ッ環(ミツカン)」とした商標です。○には、易学上の理論にある「天下一円にあまねし(隅々まで広く行き渡るように)」という意味が込められています。この商標は、1887年5月26日に登録を完了し、現在まで受け継がれています。
3. まとめ
私たちは毎日、多くの商品を手にしています。それぞれの製造メーカーには長い歴史があり、商標にはさまざまな思いが込められています。
今回ご紹介した3つの商標以外にも、数多くの商標が登録されています。食事をしながら、身の回りにある商標について調べてみると、新しい発見があるかもしれません。
商標の背景にある歴史や文化を知ることで、普段使っている商品への愛着も深まることでしょう。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247