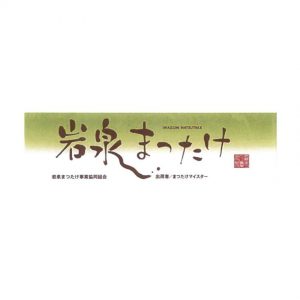1. 岩泉まつたけ:森林が育む秋の贈り物
マイスターが守る品質基準
岩手県岩泉町は、その93%が森林に覆われています。美しい清流とアカマツ林のなかで育まれる「岩泉まつたけ」は、町の特産品として地域経済を支えています。
岩泉町では10年以上松茸の仕事に携わってきた人を「岩泉まつたけマイスター」として認定しています。
このお墨付きをもらったものだけが「岩泉まつたけ」を名乗ることができます。マイスター制度により、品質の一定水準が保たれ、消費者の信頼を獲得しています。
岩泉町は本州の北に位置していることから、ほかの産地より早く出荷されます。味と香り、形状において優れた松茸を、ひと足早く味わえることが岩泉まつたけの特徴です。出荷時期の優位性は、市場における競争力を高める要因となっています。
地域文化と結びついた特産品
岩泉町の合の山(あいのやま)には、「岩泉松茸神社」があります。全国でもめずらしい神社で、狛犬の代わりに松茸のモニュメントが訪れる人を迎えてくれます。収穫の時期には多くの人が足を運び、豊作を願うそうです。
地域の特産品が神社として祀られていることは、松茸が単なる商品ではなく、地域の文化や信仰と深く結びついていることを示しています。
このような文化的背景は、ブランド価値を高める重要な要素となっています。
商標登録による保護戦略
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
「岩泉まつたけ」は、2012年1月に商標登録されています(商標登録 第5463948号)。その後、2017年3月には、新たに地域団体商標として登録されました(商標登録 第5931806号)。
地域団体商標制度は、2006年4月から始まった制度です。
それまでの商標法では、地名は一個人に独占されるものではないという考えから、「地名+商品内容」だけの商標では登録が困難でした。
地域団体商標制度により、その土地で生産された商品や伝統工芸品、温泉やご当地グルメなどのサービスも登録できるようになりました。地元の人々が自身の手でブランドを守り、育てることができる仕組みが整備されたのです。
2. 大黒さんま:厳格な選別基準が生む価値
漁師の技術と誇りが支える品質
北海道南東部に位置する厚岸(あっけし)町は、自然に恵まれた歴史ある街です。古くから「牡蠣の街」として知られており、アイヌ語で「牡蠣の漁場」を意味する「アツケシ」が転じて町名になったという説もあります。
太平洋に面した厚岸沖は、寒流と暖流、親潮と黒潮が交わる場所であり、豊富な海の幸に恵まれています。
味と鮮度を誇る厚岸のさんまのなかでも、さらに厳しい規定に合格したものだけが「大黒さんま」を名乗ることができます。
厚岸のさんま漁では、船上で特大のものだけを選別し、直ちに箱詰めされます。この鮮度保持のための徹底した対策は、漁獲から流通までの一貫した品質管理体制を構築しています。
選別基準の明確化と鮮度管理の徹底により、市場での差別化に成功しています。
商標登録による競争優位の確立
「大黒さんま」は、2011年4月に地域団体商標として登録されました(商標登録 第5407849号)。その後、図形付きの商標も登録されています(商標登録 第5414982号)。
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
複数の商標登録により、文字商標と図形商標の両面から保護を受けることができます。これにより、模倣品や類似品から「大黒さんま」ブランドを守る体制が整備されています。
3. 厚保くり・中山栗:伝統と品質管理の融合
250年の歴史を持つ厚保くり
山口県美祢市厚保地区は、県内有数の栗の産地として知られています。その歴史は250年におよび、大ぶりで甘みのある「厚保くり」は、全国でも人気があります。
収穫された栗は、まず生産者によって選別され、小ぶりなものや虫食いのあるものは外されます。
選果場へ運ばれた後、もう1度規格を満たしているか確認されます。このとき約3分の1が規格外になるという厳しい選別基準により、品質の均一性が保たれています。
「厚保くり」は、地域団体商標制度が施行された2006年に出願され、2008年2月に登録されました(商標登録 第5109216号)。早期の商標登録により、ブランドの先行者利益を確保しています。
地理的優位性を活かした中山栗
瀬戸内海に面した愛媛県伊予市は、3つの地区(伊予地区、双海地区、中山地区)からなる豊かな自然に囲まれた街です。
特産品も多く、伊予地区ではみかんや唐川びわ、チリメン、双海地区ではじゃこてんなどが人気を集めています。
中山地区で栽培されている「中山栗」は、中山間部特有の昼夜の寒暖差を活かして生産されています。この地理的条件により、大粒で上品な甘みのある栗が生産されています。
「中山栗」は、2013年3月に地域団体商標として登録されました(商標登録 第5565057号)。地理的優位性と商標登録を組み合わせることで、競合他社との差別化を図っています。
4. まとめ:商標登録が守る地域の価値
食卓に並ぶ秋の味覚には、それぞれの地域の特性や生産者のこだわりが込められています。商品のブランドについても、関係者の手でしっかりと守り続ける必要があります。
第三者に商品名を勝手に使われ、味や品質の劣るものが食卓に並ぶようになれば、本物の価値も下がってしまいます。商標登録により、品質基準を満たさない商品から消費者を守ることができます。
地域団体商標制度は、地域の生産者が団結してブランドを守る仕組みです。マイスター制度や厳格な選別基準と組み合わせることで、品質の維持と向上を図ることができます。商標登録は、地域の特産品が持つ文化的価値や歴史的背景を保護し、次世代へ継承していくための重要な手段となっています。
丹精込めた品が消費者の元に届けられ、多くの人が季節の味を堪能するためにも、商標登録は欠かせないものとなっています。
地域の特産品を守り、育てていくための法的基盤として、商標登録の重要性はますます高まっています。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247