索 引
1. 商標権侵害の基本概念
商標権とは、特許庁への商標登録出願と審査を経て発生する独占的な権利です。
企業や個人が商品やサービスに使用する名称、ロゴ、マークなどを保護する制度として機能しています。この権利の特徴は、権利の存在を知らなくても侵害行為をすれば法的責任を問われる点にあります。
商標権は私有地に設定される土地の権利と似た性質を持っています。誰でも入れる公有地とは異なり、私有地には所有者の許可なく立ち入れません。
同様に、商標権で保護された範囲に無断で踏み込むと、商標法違反として法的措置の対象となります。土地への不法侵入が罰則の対象となるように、商標権の権利範囲に無断で入り込むことも違法行為として扱われます。
商標権侵害に該当する行為
商標権は、商標権者が登録商標やそれに類似する商標を、指定商品や指定役務の範囲内で独占的に使用できる権利です(商標法第25条、第37条第1項第1号)。この独占的使用権には、専用権と禁止権という二つの権利範囲が含まれています。
商標権者から使用許諾を受けた者による登録商標の使用は、当然ながら侵害行為には該当しません。
一方で、独占排他的な使用権とは、商標権者以外の者が無断で権利範囲内の商標を使用した場合、裁判所への訴訟提起や警察への罰則適用要請が可能になることを意味します。
登録商標は特許庁に登録されている商標そのものを指します(商標法第2条第5項)。
商標権は登録商標に対して無制限に発生するわけではなく、登録時に指定した商品やサービスの範囲内で効力を持ちます。
この権利範囲は専用権と禁止権の二つで構成されており、それぞれ異なる保護範囲を持っています。
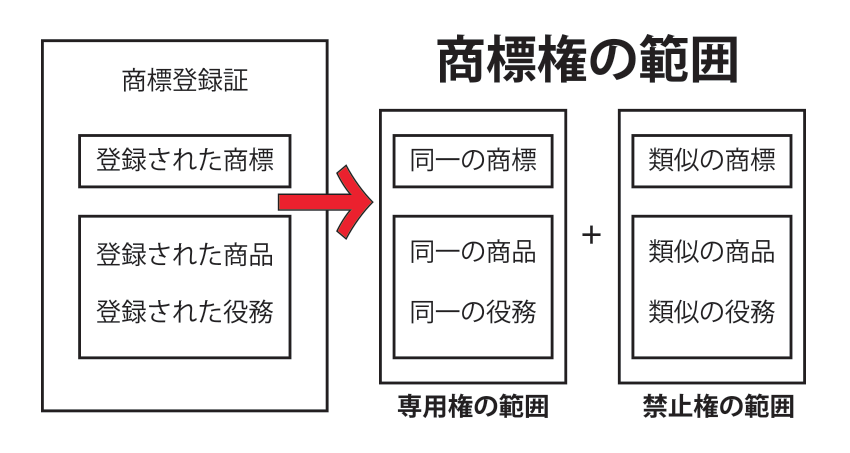
専用権の範囲での侵害行為
専用権は商標権の中核部分であり、登録商標と同一の商標を、指定商品または指定役務と同一の商品またはサービスに使用する権利です。
この範囲内での無断使用は、直接的な商標権侵害となります。専用権の内容は商標登録証に明記されているため、権利範囲を把握しやすいという特徴があります。
禁止権の範囲での侵害行為
禁止権は専用権を取り囲むように設定される保護範囲です。登録商標に類似する商標の使用や、指定商品・役務に類似する商品・サービスでの使用を禁止する権利となっています。この禁止権は以下の三つのパターンに分類されます。
- 登録商標と同一の商標を、指定商品・役務と類似する商品・サービスに使用する場合
- 登録商標と類似する商標を、指定商品・役務と同一の商品・サービスに使用する場合
- 登録商標と類似する商標を、指定商品・役務と類似する商品・サービスに使用する場合
これらのいずれかに該当する使用行為は、商標権侵害として扱われます。
具体的な侵害行為の例
商標権侵害となる具体的な行為には様々なケースがあります。
Tシャツの首部分のタグに商標を表示する行為、お菓子の包装紙に商標を印刷して商品を包装する行為、タクシーの車体側面に商標を表示して営業する行為、飲食店で使用する食器類に商標を表示する行為などが該当します。
これらは全て、専用権または禁止権の範囲内での商標使用として、侵害行為と認定される可能性があります。
侵害の予備行為
直接的な商標の使用でなくても、商標権侵害となる場合があります。
指定商品用の類似商標を付した包装紙を譲渡目的で所持する行為や、商品に表示する前の商標エンブレムを侵害目的で所持する行為は、予備行為として商標法違反となります(商標法第37条各項)。
これらの行為は商標を商品やサービスに直接使用していないため直接侵害ではありませんが、間接侵害として扱われます。
専用権や禁止権の範囲外であっても、侵害の準備行為として法的責任を問われる可能性があることに注意が必要です。
2. 商標権侵害の判定基準
商標権侵害の判定には明確な基準が存在します。対比する商標同士の類似性と、商品・サービスの類似性を総合的に判断し、登録商標の権利範囲に含まれるかどうかを検討します。
侵害となる判定パターン
商標権侵害と認定される組み合わせは四つのパターンに分類されます。
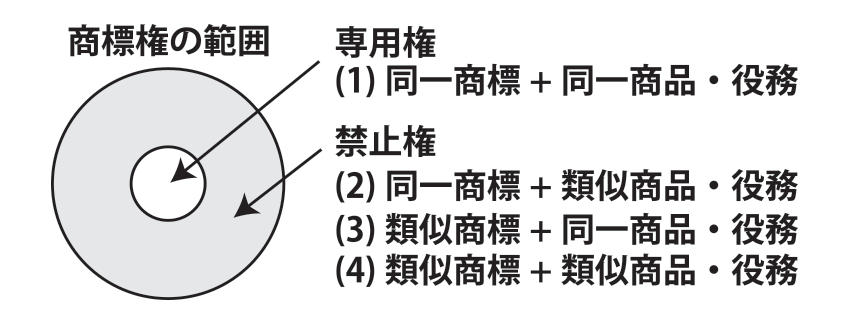
- 商標が同一で商品・サービスも同一の場合
- 商標が類似で商品・サービスが同一の場合
- 商標が同一で商品・サービスが類似の場合
- 商標が類似で商品・サービスも類似の場合
これらのいずれかに該当すれば、商標権侵害の可能性が高くなります。
侵害とならない判定パターン
商標権侵害に該当しないケースも明確に定められています。
商標も商品・サービスも非類似の場合、商標は同一でも商品・サービスが非類似の場合、商標は類似でも商品・サービスが非類似の場合、商標は非類似で商品・サービスが同一または類似の場合です。
つまり、商標と商品・サービスのうち少なくとも一方が非類似であれば、原則として商標権侵害には該当しません。
逆に言えば、両方が類似または同一の関係にある場合のみ、侵害の可能性が生じることになります。
商標の類似性判断
商標同士の類似性は、外観、称呼、観念という三つの要素から判断されます。これらの要素のうち一つでも共通していれば、原則として商標は類似すると判断されます。
商標の外観
外観とは商標の見た目を指します。例えば、大文字の「I」と小文字の「l」は読み方や意味は異なりますが、視覚的に似ているため外観が類似していると判断されます。フォントやデザインによっては、異なる文字でも見た目が酷似する場合があり、このような場合も外観類似として扱われます。
商標の称呼
称呼とは商標の読み方を意味します。「ヤマセ」と「山清」は見た目や意味は異なりますが、読み方が同じため称呼が類似していると判断されます。日本語の場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など表記方法が多様なため、称呼の類似性は特に重要な判断要素となります。
商標の観念
観念とは商標が持つ意味や印象を指します。「School」と「学校」は読み方も見た目も異なりますが、同じ意味を持つため観念が類似していると判断されます。異なる言語で同じ意味を表す言葉や、同じ概念を表す異なる表現も観念類似として扱われる可能性があります。
最終的な類似性判断では、これら三要素を総合的に検討し、一般消費者の視点から出所混同の恐れがあるかどうかを判断します。
一つの要素が一致していても、他の要素が明確に異なり混同の恐れがない場合は、非類似と判断されることもあります。
例えば「橋」と「箸」は称呼は同じですが、日常生活で明確に区別されているため、通常は非類似と判断されます。
商品・サービスの類似性判断
商品やサービスの類似性は、主に出所混同の可能性を基準に判断されます。取引の実情を考慮し、消費者が同一の事業者による商品やサービスと誤認する可能性があるかどうかを検討します。
例えば、商品の販売場所とサービスの提供場所が一致している場合、商品とサービスという違いがあっても類似すると判断される場合があります。「電子出版物」という商品と「電子出版物の提供」というサービスは、密接な関連性があるため類似すると推定されます。このように、商品とサービスの性質、用途、販売チャネル、対象顧客などを総合的に考慮して類似性を判断します。
3. 商標権侵害のリスクと影響
法的リスク
商標権を侵害すると、権利者から様々な法的措置を取られるリスクがあります。これらの措置は裁判所の判決を前提としており、企業活動に深刻な影響を与える可能性があります。
商標使用の差止請求は、最も直接的な法的措置です。
商標の使用中止を命じられた場合、商品パッケージの全面変更が必要になることがあります。商品本体に商標が表示されている場合は、全商品からシールを剥がすなどの作業が必要となり、数万個以上の在庫があれば対応は極めて困難になります。
結果として、事実上の営業停止や商品販売中止、在庫商品の破棄を余儀なくされる場合があります。
付帯物の破棄も命じられることがあります。
店舗の看板、食器類、箸袋などの店舗付帯物、名刺、ポスター、チラシ、カタログなどの営業付帯物、ウェブサイトやオンラインショップに表示されているロゴやマークなどの電子的付帯物も対象となります。これらの変更や破棄には多大なコストと時間がかかります。
社名や商品名の変更を余儀なくされることもあります。
会社名は「普通に表示される方法」であれば使用可能ですが、デザイン化したり省略したりすると侵害となる場合があります。
長年使用してきた商品名を変更すれば、顧客の認知度がリセットされ、ブランド価値が大きく損なわれます。多額の広告費や開発費を投じた後に商標が使用できなくなれば、投資が全て無駄になってしまいます。
経済的リスク
損害賠償請求は過去の侵害行為に対しても行われます。
現在商標の使用を中止していても、過去の使用分について賠償責任を負う可能性があります。
商標法では、権利者の損害立証を容易にするため、単位利益×譲渡個数を損害額と推定する規定(商標法38条1項)、侵害者利益額を損害額と推定する規定(同38条2項)、ライセンス料相当額を損害額と推定する規定(同38条3項)が設けられています。
信用回復措置として、謝罪広告の掲載を求められることもあります。新聞や業界誌への謝罪広告掲載には費用がかかるだけでなく、企業イメージへの悪影響も避けられません。
商標権の高額買取を要求されるケースもあります。事業継続のために商標使用が不可欠な場合、不利な条件での買取に応じざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
刑事罰のリスク
商標権侵害には刑事罰も適用されます(商標法78条)。
個人の場合、10年以下の拘禁もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人の場合、実行者個人への刑事罰に加え、法人に対して3億円以下の罰金が科されることがあります(商標法82条)。
社会的リスク
ブランディングの低下は避けられません。
商標権侵害で警察に逮捕されたり、トラブルが公になったりすれば、企業の信頼性は大きく損なわれます。取引先からの信用を失い、顧客離れが進む可能性があります。
管理体制の甘さを指摘され、コンプライアンス体制の見直しを迫られることもあります。上場企業の場合、株価への悪影響も懸念されます。
精神的な負担も無視できません。「侵害者」「パクリ」といったレッテルを貼られ、ネット上で情報が拡散すれば、長年築いてきた信用を一瞬で失うことになります。経営者や担当者の精神的ストレスは計り知れません。
4. 商標権侵害で警告された場合の対応
商標権侵害の警告を受けた場合、適切な初動対応が極めて重要です。警告は通常、内容証明郵便による警告書という形で届きます。
専門家への相談
警告書を受け取ったら、まず商標権の専門家である弁理士に相談することが重要です。
警告内容が妥当でない可能性や、権利者側に誤解がある可能性もあるためです。
自己判断で対応すると、本来払う必要のないコストを負担したり、不利な約束をしてしまったりする危険があります。
確認すべきポイント
相手が本当に商標権者かどうかの確認
差止請求ができるのは商標権者本人か専用使用権者に限られます。通常使用権者や第三者からの警告には法的根拠がないため、正当な権利者からの連絡を求める必要があります。
侵害の事実確認も重要
主張されている商標使用の事実があるか、何らかの行き違いがないかを確認します。商標の同一性・類似性については、外観、称呼、観念の三要素から慎重に検討します。類似していると思われる場合は、取引実態を示す資料を準備して弁理士と相談します。
商品・サービスの類似性も検討対象
商標が一致していても、商品やサービスが全く関係なければ原則として侵害になりません。ただし、商標を表示する物を所持する行為は指定商品・役務と関係なく侵害となる場合があるため注意が必要です。
出所混同の有無も重要な判断要素です。形式的には侵害に見えても、実際に混同が生じていない特別な事情があれば、裁判で考慮される可能性があります。
警告された商標が普通名称化していないか、過誤登録でないか
「うどんすき」や「恵方巻」のように普通名称化した商標は、権利行使が認められない場合があります。また、本来登録されるべきでなかった商標の権利行使は、権利濫用として認められないことがあります。
商標権侵害品の転売リスク
商標権侵害品の輸入、転売、ネットオークションでの販売は、事前警告なしに警察に逮捕される可能性があります。証拠隠滅を防ぐため、いきなり逮捕されることもあります。他に転売者がいても、自分が逮捕されない保証はありません。
5. 商標権を侵害されている場合の対応
自社の商標権が侵害されている場合、権利者として様々な対応が可能です。
民事的措置
差止請求権(商標法36条)により、侵害行為の停止、侵害品の廃棄、侵害に使用された設備の除去などを求めることができます。裁判所で認められれば、相手方の商品流通を停止させることが可能です。
損害賠償請求(民法709条)は、侵害者に故意・過失がある場合に可能です。
商標法では損害立証の困難さを考慮し、特別な推定規定が設けられています。単位利益×譲渡個数での算定、侵害者利益額での算定、ライセンス料相当額での算定が可能です。ただし、請求者の供給能力なども考慮されるため、必ずしも満額が認められるわけではありません。
不当利得返還請求(民法703、704条)により、本来権利者が得るはずだった利益の返還を求めることも可能です。信用回復措置請求(商標法39条、特許法106条準用)として、謝罪広告の掲載を求めることもできます。
請求権の時効
損害賠償請求権には3年の時効があることに注意が必要です。訴訟を躊躇している間に時効期間が経過すると、請求できなくなります。
6. 実際の商標権侵害事例
近年の商標権侵害事件では、高額な損害賠償が認められるケースが増えています。
「にじいろクリニック」事件
「にじいろクリニック」事件では、医療クリニックサービスに関する商標権侵害で約2000万円の損害賠償が認められました(知的財産高等裁判所、令和7年2月6日判決)。
「パクとモグ」事件
「パクとモグ」事件では、ミールキット宅配サービスに関する商標権侵害で、売上の1%をロイヤルティとして約510万円の損害賠償が認められました(東京地方裁判所、令和7年1月24日判決)。
「Robot Shop」事件
「Robot Shop」事件では、ロボット部品等のオンライン小売サービスに関する商標権侵害で、損害賠償約1100万円、不当利得約250万円が認められました(大阪地方裁判所、令和5年12月14日判決)。
「明光義塾」事件
「明光義塾」事件では、学習塾等の教育サービスに関する商標権侵害で約3億5000万円という巨額の損害賠償が認められました(東京地方裁判所、令和7年3月14日判決)。
これらの事例は、商標権侵害が企業に与える経済的影響の大きさを示しています。
7. 商標権侵害を防ぐための対策
商標権侵害トラブルを避けるためには、自社で商標権を取得することが最も確実な方法です。
商標登録の重要性
特許庁の審査に合格した商標は、原則として他人の商標権を侵害しないことが確認されています。
これは国による一定の保証といえます。
商標法第25条により、商標権者は登録商標を独占的に使用する権利が認められています。無効や取消になるまでは、専用権の範囲内での使用が法的に保護されます。
先願主義のリスク
日本の商標制度は先願主義を採用しています。どれだけ長く商標を使用していても、特許庁に最初に出願した者が商標権者となります。
商標権を持たない状態で使用を続けると、後から商標権を取得した第三者から侵害を主張されるリスクがあります。
商標登録は早い者勝ちの制度です。先に商標権を取得しておけば、他人がその商標権を消滅させない限り、同一または類似の商標を取得することはできません。商標権の取得を怠ると、将来的に大きなリスクを抱えることになります。
裁判での対応の重要性
万が一商標権侵害で訴えられた場合、最も避けるべきは裁判所に出頭せず、相手の主張に反論しないことです。民事裁判では、反論しなければ相手の主張が全て認められてしまいます。
例えば、1億円の損害賠償を請求されて裁判を無視した場合、実際に1億円の支払い判決が確定してしまいます。何もしないという対応が最も高くつくことを認識し、必ず専門家と相談の上で適切に対応することが重要です。
商標権は企業活動において重要な知的財産です。適切な権利取得と管理により、安心してビジネスを展開できる環境を整えることが、長期的な事業成功への第一歩となります。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

